デジタル変革で生き残る
~製造業DXへの挑戦~

2025年4月2日
製造業にとってDXは、競争力を維持し、未来を切り拓くために避けて通れない道です。最新技術を活用し、効率化と品質向上を実現することで、新たな成長につなげることができます。本コラムでは製造業DXについて、基礎から推進の方法、具体例や将来展望まで幅広く解説します。
製造業DXの基礎知識
製造業DXとは、「デジタル技術を活用して製造業のプロセスやビジネスモデルを革新すること」を指します。これにより、効率化、品質向上、コスト削減が実現され、競争力が強化されます。具体的には、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)、ビッグデータ解析などの技術を導入し、スマートファクトリーの構築や予知保全の実施が可能になります。製造業DXは、企業が市場の変化へ迅速に対応し、成長を続けるために必要な戦略の1つとなりつつあります。
さらに、DXを推進する背景として、企業はグローバル競争の激化、顧客ニーズの多様化、そして技術の急速な発展による市場の変化に対応し、効率的かつ柔軟な生産体制を構築する必要があります。さらに、環境問題への対応や持続可能な経営が求められる中で、デジタル技術を活用することで、資源の最適利用やエネルギー効率の向上が可能になります。これにより、企業は競争力を維持しつつ、社会的責任を果たすことにもつながることが背景にあげられます。
なぜ製造業DXが注目されているのか
急速に変化する市場環境の中、製造業も生き残りをかけて経営モデルを見直す動きが高まっています。DXは既存製造プロセスの効率化だけでなく、新規ビジネスの可能性や差別化戦略を生み出す大きな手段となります。後述するメリットの中でも、業務効率化や生産性向上、データ活用による経営基盤強化などインパクトが大きく、多くの企業が、導入を検討しています。
経営環境の変化と市場の成熟化
消費者の購買行動もオンラインを活用し情報収集するなど、変化が著しいです。こうした経営環境の変化や市場の成熟化に対し、新たな手段で対応することが求められています。
人材不足への対応
多くの工場や生産現場では、定年による熟練技術者の退職の増加、それに対し若手の補填が追い付いていないという現象が起きています。
そこでDXを活用し、ロボットや自動制御システムを導入して省人化を進めることにより、限られた人材で、利益を最大化する動きが活発になってきています。
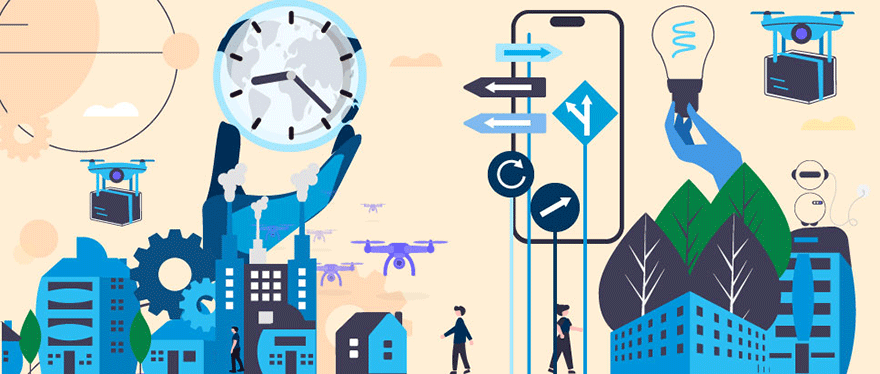
期待される4つのメリット
導入による期待されるメリットは多岐にわたります。大きく分けると「業務効率化と生産性向上」、「データ活用による経営判断の高度化」、「新たな価値創造による差別化」、そして「顧客満足度の向上」の4つが挙げられます。
-
業務効率化と生産性向上
導入した製造ロボットやAI分析により、製造ラインの稼働率を最適化しムダを削減できます。また、単純作業や危険作業を機械に任せることで、ヒューマンエラーを削減し、安全性も大幅に向上します。これらのプロセス改善は、コスト削減や付加価値の高い業務へのリソース再配分につながるため、多くの企業が注目しています。
-
データ活用による経営基盤の強化
ビッグデータやクラウド上の分析ツールを活用することで、経営陣は迅速かつ的確な意思決定を下すことが可能となります。
需要予測や在庫管理をリアルタイムで最適化することで、不必要な在庫を減らし販売機会を逃さない体制を構築することができます。また、組織全体のデータを一元管理することで、横断的な分析が可能となり、経営戦略や新製品開発にも体系的な改善効果が期待できます。
-
サービスの差別化と新しい価値創造
蓄積されたデータやノウハウを活用することで、顧客の潜在ニーズを掘り起こした、新たなサービスを生み出すことが可能となります。
例えば、自社製品に継続的な保守サービスを付帯させるサブスクリプションサービスも新たな収益源になります。こうした差別化を図ることにより、顧客との長期的な関係を築くことができます。
-
顧客満足度の向上
受注から生産、納品までのリードタイムを可視化・短縮することで、顧客が必要とする時期に、製品を供給しやすくなります。また、迅速なトラブル対応や不具合の予防をデータで行うことで、品質面での信頼感も高まります。結果的に顧客満足度の向上につながり、リピート率やブランドロイヤルティも向上していきます。
進め方と実践方法
DXを円滑に進めるためには、初期の段階で全体的なビジョンを定め、ステップを明確にしながら計画を策定していくことが大切です。
特に、小さな成功を積み重ねるスモールスタートは、新しい技術に対する現場の理解と受容を高める上でも効果的であると言えます。
以下より、その進め方や実際の技術活用事例を解説致します。
-
DX推進を目的としたビジョンの設定
企業として実現したい姿を明確に描くことが重要です。例えば、「新しいビジネスモデルの構築を目指す」や、「生産効率と品質を極限まで高めたスマートファクトリーを目指す」など、大枠のゴールを設定します。こうしたビジョンは、全社で共有し、経営陣が旗振り役となることが重要です。
-
戦略の策定と計画の具体化
ビジョンを基に、実際にどの部門でどんな技術を導入するのかなど、具体的なロードマップを描きます。
生産ラインのIoT化から始めるのか、サプライチェーン全体の最適化を狙うのか、優先度を整理して予算やスケジュールを設定することが重要になります。最初から完璧を求めず、確認しながら徐々に拡散していくことが大切です。
-
スモールスタートの重要性
大規模なシステム導入は、多額の投資と大きな組織改編を伴い、失敗時のリスクが高まります。スモールスタートは、まず小さな範囲で問題点を洗い出し、その成果や改善点を積み上げながら展開するので、現場の抵抗も少なくて済みます。成功体験を繰り返すことでモチベーションも高まり、息の長い推進につながります。
製造業DXの事例から学ぶポイント
DXを導入して成果を上げている事例や、失敗に終わった事例を分析しながら成功のポイントを探ります。成功事例を知ることは、自社DXを円滑に進める上で非常に大切です。一方、失敗から学ぶことで導入時の落とし穴を回避しやすくなります。ここでは、国内外の具体例を通じ、各社の戦略や実施プロセスを見ていきます。
成功事例とその分析
大手企業のみならず、中堅・中小企業でもDXに成功しているケースがあります。事例を分析すると、明確なビジョン設定と段階的な導入、そして経営層と現場の円滑なコミュニケーションが共通点として見られます。コスト・時間、そして計画的な人材育成を怠らなかった企業が、大きな成果を得ています。
1. 工場IoTの導入
自動車メーカーA社は、工場IoTを導入し、生産現場のデジタル化を進めています。まず、3D CADデータなどのデジタルデータを一元管理し、情報共有基盤を構築しました。次に、現有資産の最大有効活用やデータ分析の効率化を図り、FA機器類からのデータ授受の有効活用を進めました。これにより、効率化と費用対効果を重視した取り組みを実現しています。
2. スマートファクトリーの実現
電機メーカーB社は、工場内で生産情報とITを連携させ、リアルタイムでデータを分析・活用する仕組みを導入しました。まず、生産設備やエッジコンピューティングによるデータ収集を行い、そのデータをリアルタイムで分析しました。サプライチェーンとも連携し、工場全体の生産性向上を目指しました。これにより、生産性の向上やコスト削減が可能になりました。
3. バーチャル工場の構築
通信メーカーC社は、複数の工場を仮想的に1つの工場として融合するプロジェクトを推進しました。まず、各工場の設計データを共通化し、生産の効率化を図りました。次に、工場間の負荷分散を可能にし、多品種少量生産のニーズに対応しました。これにより、コスト削減と外部環境変化への対応力が強化することができました。
しかしながら、全社的なコンセンサスを得ないままシステムだけ導入し、現場が使いこなせずに終わるケースも多々あります。こうした失敗は、目的設定やロードマップが曖昧なまま進行し、現場目線での運用設計不足などが原因となります。この失敗事例により、経営層と現場、そしてIT部門の三位一体の連携が重要であることがわかります。
DXがかなえる未来
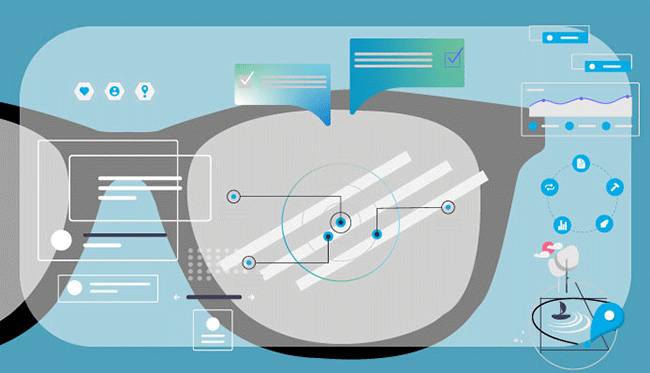
製造業におけるDXの浸透が、将来どのような企業価値や社会的影響をもたらすのかについて展望します。製造業DXが進むことで、単なる製造効率の改善だけではなく、ビジネスモデル自体が大きく変革される可能性があります。例えば、顧客のニーズをリアルタイムに反映し、オンデマンド生産を行うことも技術的には可能になっていくと推測されます。
-
次世代の競争力を支える
高度なデジタル技術と生産プロセスの管理ノウハウを組み合わせることで、製造業は新しい価値を市場に提供できます。顧客との共同開発や、サプライチェーンを越えたアライアンスを通じて、差別化されたサービスやプロダクトを打ち出すことも可能になります。こうした取り組みが、競争力を強化することにつながります。
-
効率的な生産体制の構築
自動化やデータ連携が進むことで、生産ラインからのロスが減り、稼働率を上げることができます。さらに、環境に配慮した素材選定や再生資源の利用など、循環型社会に適応する取り組みにシフトしやすくなります。このように、コスト効率と環境配慮を両立できる生産体制を整えれば、企業のブランド価値を高めつつ長期的に社会貢献も実現できるはずです。
-
製造業におけるDX推進のグローバル化の流れ
国や地域を越えたビジネスのスピードが加速しており、各国の製造業が、新技術への投資を積極的に行っています。日本企業も品質や技術力に強みがある一方、海外勢が主導権を握るクラウドサービスやAIプラットフォームを活用しなければ競争が難しくなる可能性もあります。今後は、グローバルパートナーとの連携や国際規格への対応など、柔軟な戦略が必要となってきます。
まとめ
製造業DXを円滑に進めるには、明確なビジョンや段階的導入の戦略立案、そして現場を含む全社的な理解と連携が重要です。さらに、人材不足を補う外部リソースや補助金・助成金の活用など、さまざまな手段を活用すると効果的です。今後も新しい技術や事例が次々と登場します。定期的に最新情報を収集し、自社の取り組みにフィードバックする文化を育むことが、製造業DXを成功へ導く鍵となるでしょう。
著者プロフィール
キヤノンシステムアンドサポート株式会社
業種ソリューション推進部 製造ソリューション推進課
森 圭央
製造ソリューション推進課の業務内容
「製造業の進化を支援しよう!」を合言葉に、日本の製造業の皆さんに寄り添い、”モーションセンサーによる作業の可視化サービス”をはじめとするさまざまなソリューションをもって進化のお手伝いを致します。
今すぐ読みたいおすすめ情報
製造業コラムについてのご相談・見積・お問い合わせ
キヤノンシステムアンドサポート株式会社


