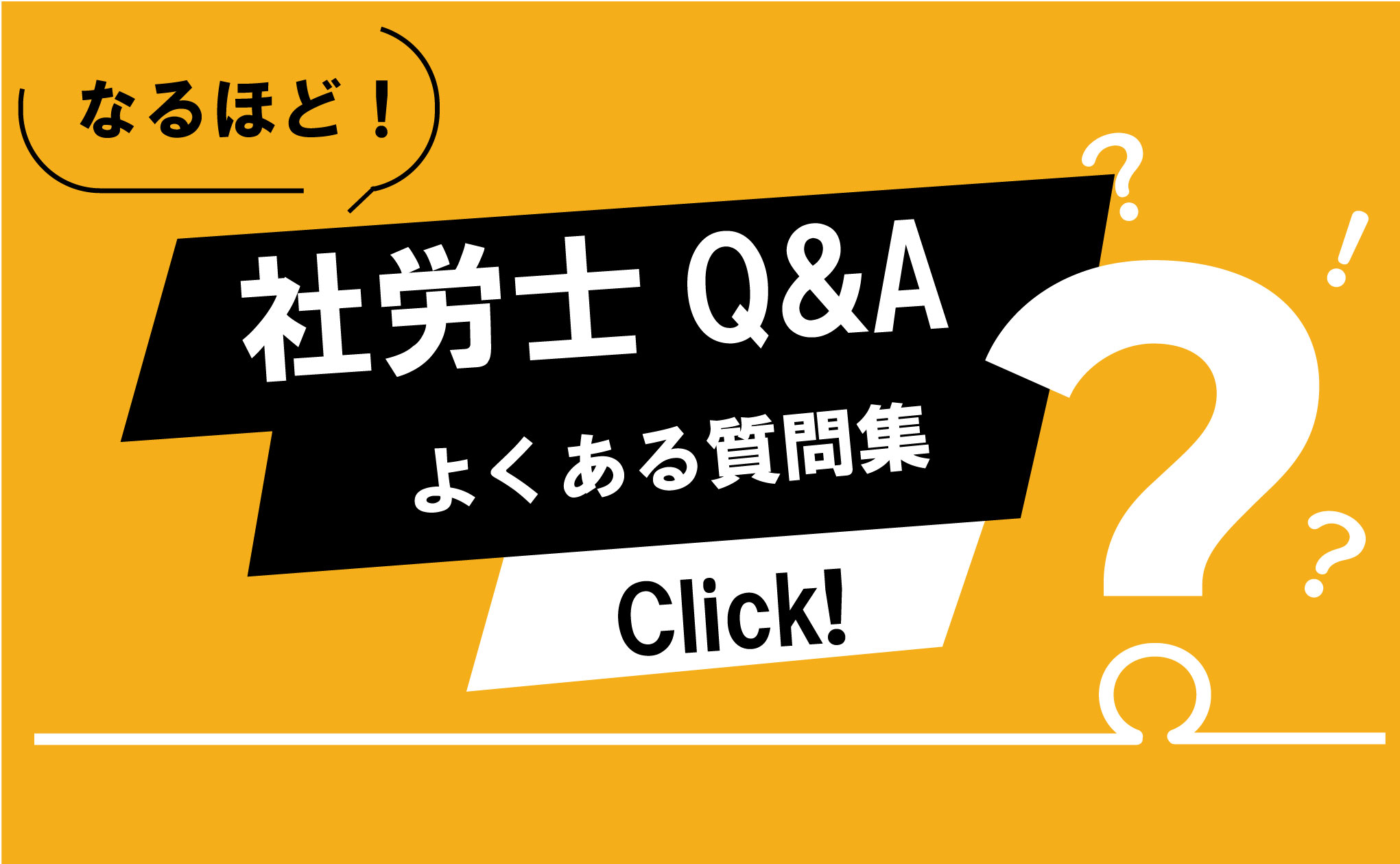「改正労働基準法」の方向性を“総まとめ”企業が備えるべき「4大テーマ」を社労士が徹底解説

2025年11月4日
更新:2026年1月20日
2025年1月に「労働基準関係法制研究会」の報告書が公表され、労働基準法の見直しに向けた議論が本格化しています。政府は働き方改革を一層推進し、多様化する現代の就労実態に即した労働環境を整備するため、労働政策審議会労働条件分科会において具体的な制度設計の議論を進めています。
本コラムでは、2026年以降の改正に向けて議論が本格化している今だからこそ知っておくべき重要論点を「4大テーマ」に整理し、その全体像と企業経営に与える影響について解説します。
-
※
本稿で解説する内容は、2025年1月8日に公表された「労働基準関係法制研究会報告書」およびその後の労働政策審議会での議論(2025年10月27日分まで)に基づく個人の見解として「方向性」をお示しするものです。今後の審議、答申、国会での法案審議を経て正式に決定されるため、成立日、施行日および改正内容等は流動的であることにご留意ください。最新情報は厚生労働省の公式サイトで必ずご確認ください。(なお、ニュースサイト等にて、現政権による「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間の規制の緩和の検討」の指示を踏まえ、さらなる議論が必要になり、2026年中の国会への法案提出が見送られるとの報道がなされています。)
改正の背景
今回の見直しの土台となっているのが、2025年1月8日に公表された「労働基準関係法制研究会」の報告書です。この報告書が今後の労働法制の羅針盤となり、これを受けて厚生労働省の労働政策審議会(労働条件分科会)が、労使の代表を交えて具体的な制度設計の議論を進めています。
これまでの議論を踏まえると、今回の見直しは単なる微調整にとどまらず、「労働者の考え方」「労働時間・休日・休息ルール」「労使コミュニケーション」といった労働基準法の根幹に関わる広範な見直しとなる可能性があり、企業実務への影響は避けられません。
そこで、労働政策審議会で議論されている主要な論点を企業実務への影響が大きい「4つのテーマ」に整理して解説します。多くの企業の労務管理に大きな影響を与える可能性がありますので、議論の方向性をしっかりと把握したうえで、あらかじめ対策しておくことが重要です。
テーマ1:労働時間・休日・休息ルールの見直し
長時間労働や休日管理の曖昧さが、企業の労務リスクとして注目されています。今後の法改正に備え、さらなる長時間労働の是正や休日のあり方、勤務体制の見直しが求められます。
(1)連続勤務の上限は「13日」へ
- 現行の課題:「4週4日の変形休日制」により、理論上、最大48日間の連続勤務が可能とされ、実務上の健康リスクが指摘されてきました。
- 改正の方向性:連続勤務の上限を13日に制限する方向で議論が進んでいます。ただし、災害復旧等の真にやむを得ない場合や安全確保等の例外を設ける案も検討されています。
- 企業への影響:製造業、運輸業、医療・介護業界など、シフト制で連続勤務が発生しやすい業種では、人員配置や勤務パターンの見直しが必須となる可能性があります。
(2)「法定休日」の特定
- 現行の課題:法定休日と法定外休日の区別が曖昧なため、休日労働の割増賃金(法定休日は1.35倍、法定外休日は1.25倍等)の計算ミスが生じやすい状況です。
- 改正の方向性:就業規則等で法定休日を事前に特定することを原則化する方向で検討されています。ただし、シフト制労働者等への対応として、いつまでに特定するか、特定後に変更できるか等の手続きも論点になっています。
- 企業への影響:週休2日制の企業は、「土曜と日曜のうち、どちらを法定休日にするか」を明確に定める必要が生じる可能性があります。給与計算システムの設定見直しも必要となる可能性があります。
(3)勤務間インターバル制度の導入促進
- 現行の課題:勤務間インターバル制度は労働時間等設定改善法上の努力義務にとどまり、導入企業も限定的です。
- 改正の方向性:勤務間インターバル制度について、抜本的な導入促進と、義務化を視野に入れた法規制の強化を検討する必要があるとされており、勤務間インターバル時間は11時間確保を原則としつつ議論されています。ただし、使用者側委員からは、仮に義務化される場合でも、一律に「11時間」とするのではなく、時間数の幅(9~11時間等)を持たせたり、業種による適用除外や中小企業への猶予期間を設けたりするなど、実態に配慮した現実的な制度設計であるべきとの意見が出ています。
- 企業への影響:シフト設計や残業の付け方を含め、インターバルを前提とした勤務パターンへの組み替えが求められる可能性があります。
(4)年次有給休暇に関する見直し
- 現行の課題:例えば、時間単位年休は、労使協定を締結した場合に限り、「年5日」を上限として取得可能ですが、育児・介護、通院等のニーズに対して不十分ではないか、など、全体として有給休暇の取得促進の取り組みが不十分との意見があります。
- 改正の方向性:時間単位年休の上限(5日)引き上げや、年休取得日の賃金について「通常の賃金」に統一することのほか、労働者側委員より、出勤率「8割要件」について「不要ではないか」との意見が示されていますが、使用者側委員からは「慎重な検討が必要」との意見が出ており、今のところ進展がありません。さまざまな議論がなされていますが、(「通常の賃金」に統一すること以外は)その他のトピックに比べますと掲載資料が少なく、現時点では限定的な議論にとどまっています。
- 企業への影響:勤怠管理システムにおける出勤率の算定方法や、年休付与ルールの見直しが必要となる可能性があります。
(5)法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
- 現行の課題:小売業・旅館業など一部事業場について、法定労働時間を週44時間とする特例が存在しています。
- 改正の方向性:これらの特例措置を廃止し、原則どおり週40時間に一本化する方向で議論が進められています。
- 企業への影響:対象事業場では、所定労働時間やシフト、残業管理の見直しが必要になる可能性があります。
テーマ2:「労働者性」の判断基準の明確化と多様な働き手への対応
フリーランスや副業人材など従来の枠組みに収まらない働き方が広がる中で、企業は「労働者性」の判断基準の見直しに備える必要があります。契約形態だけでなく、実態に基づく対応が求められる時代に入っています。
- 現行の課題:プラットホームワーカーやギグワーカー等、実態は労働者に近いのに法的保護を受けにくい「名ばかり事業主」問題が指摘されています。
- 改正の方向性:契約形式ではなく、実態(指揮命令の有無、拘束性、報酬の性格など)に基づいて労働者性を適切に判定できるよう、判断基準の明確化(判断要素の整理・現代化)が検討されています。他方、副業・兼業者の労働時間管理については、労働時間規制のうち「割増賃金の支払い」については、通算規定を「見直す」議論がされています。(健康管理(長時間労働への対応)」については、引き続き通算して把握する仕組みを維持することで検討が進んでいます。)
-
企業への影響:
-
(1)業務委託契約で業務を依頼しているフリーランス等について、労働者性が認められるリスクがないか再点検が必要になります。
-
(2)契約形式だけでなく、実態に基づく労働者性の判断がより重視される方向性です。
-
(3)副業・兼業者の労働時間管理について、ルールの簡素化により副業・兼業のほか、スポットワークの活用が促進される可能性があります。
-
テーマ3:「過半数代表者」制度の見直し
労使協定の正当性を支える「過半数代表者」の選出方法が、今後法改正によって厳格化される可能性があります。企業としては、選出プロセスの透明性と適正性を確保することがリスク回避の観点からも重要です。
(1)選出手続きの法制化・厳格化
- 現行の課題:「会社が一方的に指名」「知らない間に決まっていた」等、民主的プロセスを欠く不適切な選出が後を絶ちません。
- 改正の方向性:選出手続き(挙手や投票といった民主的な手続き)を法律で明確化する方向で議論されています。現在は労働基準法施行規則に規定されている選出手続きを、労働基準法本体に格上げすることが検討されています。
- 企業への影響:自社の選出プロセスが民主的か、透明性があるかなど、総点検が必要です。
(2)不適切な選出における労使協定の効力
- 現行の課題:選出手続きに不備があった場合の労使協定の効力について、法律上の規定が明確ではありません。
- 改正の方向性:労働者側委員からは、手続きに不備がある場合、36協定などが無効となるべきことを法律で明確に規定するとの意見が出されています。ただし、この点については引き続き慎重な議論が必要な論点となっています。
- 企業への影響:過半数代表者の選出手続きに瑕疵(かし)がある場合、労使協定が無効となり、通常の労働時間制度に基づく割増賃金の支払いを求められた裁判例は既に存在します。今回の法改正により、このリスクがさらに高まることが予想されます。
(3)過半数代表者の活動時間の確保・情報提供の充実
- 現行の課題:過半数代表者が役割を果たすための活動時間や情報提供が十分に確保されていないケースがあります。
- 改正の方向性:過半数代表者への活動支援として、企業には活動時間の確保や必要な情報(労働時間データなど)の提供が求められる方向で議論が進んでいます。あわせて、不利益な取り扱いの禁止規定を明確化・強化することも検討されています。
- 企業への影響:過半数代表者への適切な支援体制(業務調整・情報提供等)の整備が求められます。(※なお、時間外労働実績等の外部公表・従業員への開示についても議論されていますが、具体的な制度設計は今後の検討課題とされています。)
テーマ4:「多様な働き方」における労働時間管理等の見直し
柔軟な働き方が広がる一方で、労働時間管理や健康確保の課題が顕在化しています。企業としては、制度の趣旨を踏まえた適正な運用と、規定の見直しが求められます。
(1)テレワーク時の労働時間管理の明確化
- 現行の課題:テレワークの普及により、ICTを活用して始業・終業時刻を記録することが容易になっているにもかかわらず、「事業場外みなし労働時間制」が、要件の確認が不十分なまま適用されているケースがあります。
- 改正の方向性:在宅勤務に限定した新たな「みなし労働時間制」の議論もありましたが、労働者側委員より強い懸念が示され、「継続的な検討が必要」となっており、実労働時間の把握による管理を基本とすることが鮮明になりつつある印象です。むしろ、勤務時間外や休日に業務連絡が入ることが常態化することを防ぐため、時間外の連絡を拒否できる「つながらない権利」について、労使で話し合いを促進するための方策(ガイドライン等)を検討することが話し合われています。
- 企業への影響:テレワーク中の労働時間管理をより厳格に行う必要が生じる可能性があります。
(2)フレックスタイム制における混在運用の明確化
- 現行の課題:現行法は「すべての労働日の始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる」建て付けですが、現行制度においてはフレックスタイム制を部分的に適用することはできず、テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にフレックスタイム制を活用しづらい状況があります。
- 改正の方向性:特定の日については、労働者が始業・終業時刻を選択するのではなく、あらかじめ就業規則等で定められた始業・終業時刻どおりに出退勤することを可能とする仕組み(コアデー)が検討されています。
- 企業への影響:部分フレックスが制度化されることで、コアデーの適法な運用が可能となる一方、使用者都合による出退勤時刻の縛りが多い場合には、労働者の裁量が実質的に確保されていないとして、フレックスタイム制そのものが認められなくなるリスクが高まると予想されます。
(3)裁量労働制の対象業務の明確化と健康確保措置の強化
- 現行の課題:対象業務が法令で厳格に規定されているため、企業において適用可否の判断が難しいとの指摘があります。
- 改正の方向性:裁量労働制を適用対象業務の拡大が議論の出発点でしたが、労働者側委員からは、令和6年4月に省令改正が施行されたばかりであることを踏まえ、「長時間労働を助長しかねない」として、まずは現行ルールの適正運用の徹底を求めるとともに、勤務間インターバル(11時間以上)、深夜業回数制限(月4回以内)等の選択肢を追加するべきとの意見が出され、健康確保の強化にむけた方向性の議論になっています。
- 企業への影響:裁量労働制における制度趣旨に沿った運用と、健康確保措置の実効性確保が重要な課題となります。
(4)管理監督者の判断基準の明確化と健康確保措置
- 現行の課題:権限なく責任だけ負う「名ばかり管理職」問題が指摘されています。また、管理監督者は労働時間規制の適用除外とされており、長時間労働に陥りやすい状況にあります。
-
改正の方向性:
管理監督者に該当するかどうかの判断基準(スタッフ管理職の扱いを含む)を明確化することが議論されています。また、長時間労働に陥りやすい管理監督者についても、一定の健康・福祉確保措置を講じることを義務付けるべきとの議論がなされています。
- 企業への影響:管理監督者の範囲・権限・待遇がその職責にふさわしいかの再点検が求められます。
改正動向を踏まえた対応
本コラムで解説した内容は、現在進行中の議論に基づく未来予測ですが、その方向性は今後の日本における「働き方」のスタンダードを大きく変える可能性を秘めています。
法改正が正式に決まってから動き出すのでは準備期間が不足する可能性があります。今回の労働基準法の見直し議論は、企業の労務管理の根幹に関わる重要なテーマです。変化を恐れるのではなくこれを機に自社の労務管理体制を見直し、より働きやすい職場環境を整備することが企業の持続的成長と優秀な人材の確保につながるのではないでしょうか。
特に、以下の4つは今すぐにでも検討されることをお勧めします。
-
過半数代表者の選出プロセスの総点検と記録化
-
シフト制勤務における連続勤務日数、長時間労働の実態把握(労災リスク対応)
-
労働時間の適正な把握と管理(労働時間の認識に抜け漏れがないか)
-
業務委託契約の内容と実態の再検証
これらの取り組みを通じて、より健全で信頼される企業づくりを進めていきましょう。
参考資料・最新情報の確認先
著者プロフィール
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約250名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。
今すぐ読みたいおすすめ情報
会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ
キヤノンシステムアンドサポート株式会社