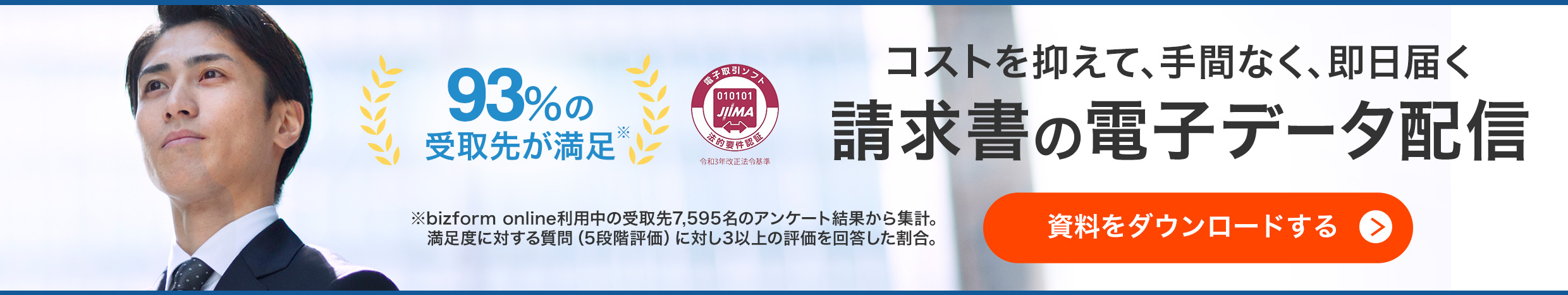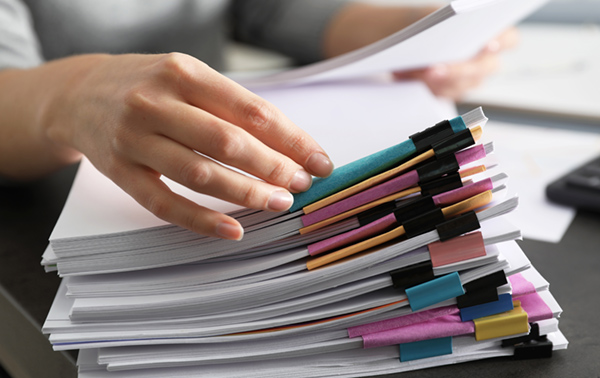物流業のDX推進。請求書電子化がもたらす業務効率化とは?

少子高齢化による労働人口減少が進む中、物流業界は深刻な人手不足に直面しています。EC市場の拡大や2024年問題による労働時間制限の影響もあり、人手不足はさらに深刻化すると予測されています。こうした課題への対応策として、注目されるのがDX(デジタルトランスフォーメーション)推進です。なかでも請求書の電子化は、煩雑な紙の処理を削減し、業務スピードを高めることでコスト削減やリソース最適化が期待されます。本コラムでは、物流業界における請求書電子化の具体的な効果と成功事例をご紹介します。
公開日:2025年4月4日
目次
-
物流業界の現状とDXや業務効率化の必要性
- 荷物の増加による業務負担の増大
- 慢性的なドライバー不足と高齢化
- 燃料費の高騰による利益率の悪化
- 2024年問題による労働時間の制限
- 物流業界のDXと業務効率化の必要性
-
物流業界の請求業務における課題
- 取引先が多く、請求書発行の件数が多い
- 請求書や明細書などの紙の発行が多い
- 経理担当者の業務負担が多く、属人化しやすい
-
物流業界における請求書の電子化のメリット
- 請求書電子化を導入するまでの4つのステップ
- 請求書電子化サービスを選ぶ際のチェックポイント
-
請求書電子配信サービス「bizform online 配信」
- 紙・印刷・郵送費などのコスト削減
- 請求書に付随する書類が添付可能に
- 担当者の業務負担の軽減
- 請求書を電子化し、業務効率化に取り組む企業の事例
- まとめ
物流業界の現状とDXや業務効率化の必要性

EC市場の拡大や2024年問題による労働時間制限などにより、物流業界では業務負担の増大や人手不足が深刻化しています。ここでは、物流業界が直面している具体的な課題や業務効率化がなぜ重要なのかについて解説します。
荷物の増加による業務負担の増大
EC市場の拡大により個人向けの配送需要が急増し、物流業界では取り扱う荷物の量が年々増加しています。2023年の日本国内のBtoCのEC市場規模は24.8兆円に達し、2013年の約21.9兆円から約13%の増加を記録しました。取り扱う荷物が増えたことで、倉庫の在庫管理の複雑化や、出荷指示・請求業務の処理件数が増加し、現場の負担はより一層重くなっています。特に紙ベースの請求書発行は、発行から送付、管理までの手間が増え、業務遅延やミスの発生につながる大きな要因のひとつとされています。
慢性的なドライバー不足と高齢化
燃料費の高騰による利益率の悪化
燃料費の高騰は、物流企業の収益を圧迫する大きな要因となっています。運送業務のコストが増加する一方で、顧客への価格転嫁が難しいため、企業の利益率が低下しているのが現状です。そのため、不要なコストを削減し、業務効率を最大化することが経営戦略の重要な課題となっています。請求業務の電子化やペーパーレス化を進めることで、印刷や郵送費の削減が可能となり、コスト最適化の一環として活用できるでしょう。
2024年問題による労働時間の制限
2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用され、1か月あたりの時間外労働は最大80時間、年間では最大960時間までに制限されました。ドライバーの稼働時間が短縮されることで物流業務全体の負荷が増すと、その影響はバックオフィス業務にも波及します。たとえば、配送遅延が発生すると請求書の発行が遅れることになり、結果的に取引先との金額調整や請求内容の見直しが必要になる場合が増えます。また、輸送コストの変動による再計算や、未回収リスクの管理など、経理担当者が対応すべき業務が増加する可能性があります。
物流業界のDXと業務効率化の必要性
物流業界では、これまで説明してきたような人手不足の深刻化を背景に、DXが加速しています。特に、自動倉庫システムの導入やAIを活用した配送ルートの最適化、ペーパーレス化などが進んでいます。しかし、物流現場の効率化が進む一方で、請求処理などの事務作業はデジタル化が遅れている企業も多いのが現状です。特に、紙の請求書を発行・管理している企業では、手作業による業務負担が増しており、業務効率化が急務となっています。
物流業界の請求業務における課題

物流業界では日々多くの取引先とやり取りを行い、大量の請求書を発行・管理する必要があります。経理担当者には膨大な業務負担がのしかかり、紙ベースの運用が続いている企業では業務の非効率化が深刻な課題となっています。ここでは、物流業界の経理業務が抱える具体的な課題について詳しく解説します。
取引先が多く、請求書発行の件数が多い
物流業界は、多数の取引先と継続的に契約を結び、毎月の取引に応じて請求書を発行する必要があります。特に、複数の荷主と契約を結ぶ運送会社や倉庫業者では、取引件数が膨大になるため、請求書の管理が大きな負担となるでしょう。
主な問題点として、以下の3つが挙げられます。
-
請求書の発行作業が煩雑
毎月数百件~数千件の請求書を発行する企業では、手作業での処理に多くの時間がかかる。
-
請求内容の確認作業が多い
取引ごとに金額や請求条件が異なるため、ミスを防ぐためのチェック作業に時間を要する。
-
入金確認や未回収管理が大変
請求書の件数が多いほど、未回収や支払い遅延の管理も煩雑になり、経理担当者の負担が増える。
さらに、取引先ごとに請求書の発行フォーマットや送付方法が異なる場合、システム化が進んでいない企業では担当者が手作業で個別対応する必要があり、業務効率が著しく低下してしまいます。
請求書や明細書などの紙の発行が多い
多くの物流企業では、請求書を紙で発行し、郵送する運用が未だに主流です。しかし、この方法には次のような課題が伴います。
-
印刷・封入・郵送に関わる手間やコストがかかる
毎月大量の請求書を発行するために、印刷や封入作業に時間を取られる。郵送費も企業にとって大きな負担。
-
請求書の紛失リスクがある
紙の請求書は取引先に届くまでに時間がかかり、紛失のリスクもある。
-
保管スペースの確保が必要
税務上の保管義務により、請求書や関連書類を長期間保管する必要があり、書類の管理コストが発生する。
特に、2024年秋に郵便料金が値上げとなり、請求書の発行通数の多い企業では郵送費の増加は大きな負担となっています。
また、請求書の紛失や配送の遅延が発生すると、支払い遅延にもつながるリスクがあり、取引先との関係にも影響を与えかねません。こうした問題を解決するためには、請求書の電子化を進め、業務の効率化を図ることが重要です。
経理担当者の業務負担が多く、属人化しやすい
物流業界の経理業務は、請求書の発行・管理だけでなく、支払い確認や取引先との調整など多岐にわたります。そのため、特定の担当者に業務が集中しやすく、業務の属人化が進んでしまう傾向があります。
-
経理担当者の負担が大きい
日々の請求処理に追われ、戦略的な業務(コスト削減や業務改善)に手が回らない。
-
引継ぎが難しい
ベテラン社員のノウハウに依存し、新しい担当者がすぐに業務をこなせない。
-
ミスが発生しやすい
請求書の作成やデータ入力が手作業で行われる場合、ヒューマンエラーが発生しやすい。
特に、経理業務の属人化が進むと、特定の担当者が退職・異動した際に業務が滞るリスクが高まります。DXが進んでいない企業では、手作業での業務が中心となるため、業務の標準化やシステム化が必要なのです。
物流業界における請求書の電子化のメリット
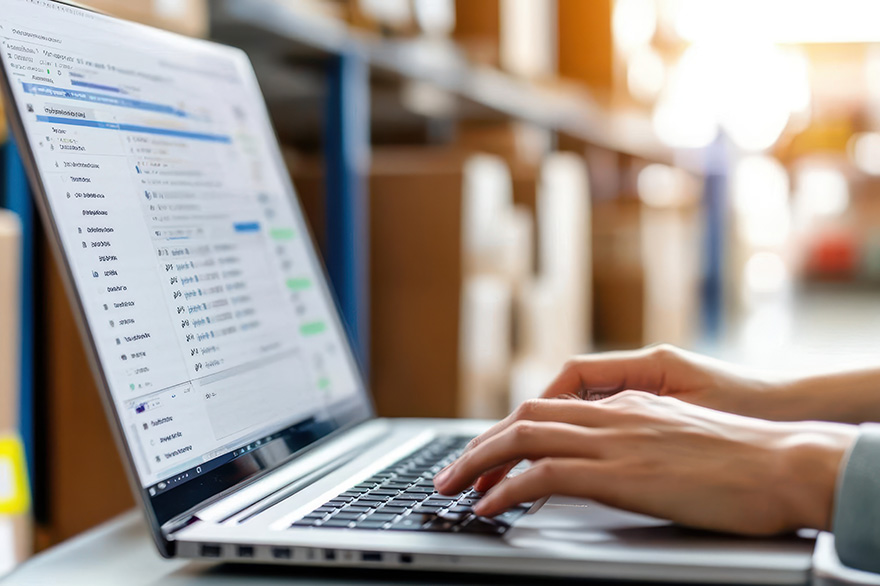
ここまでで述べたように、物流業界では「取引先の多さ」「紙の請求書の管理」「経理業務の属人化」などの課題は、経理担当者の大きな悩みの種となっています。
物流業界における請求書の電子化は、次のように大きなメリットがあります。
-
コスト削減
まず、紙の請求書を電子化することで、印刷や郵送にかかるコストを大幅に削減できます。紙の請求書では、印刷代や郵送費、封入作業の人件費などが発生しますが、電子化することでこれらのコストを削減し、経費の最適化が図れます。 -
業務スピードの向上
また、請求書の電子化により、業務のスピードと正確性が向上します。紙の請求書では、発行から送付、受領までに時間がかかり、紛失や遅延のリスクも伴います。しかし、電子請求書であれば、即時に発行・送付が可能で、取引先も迅速に確認できます。 -
業務の効率化
さらに、電子化された請求書はデータとして保存されるため、検索や管理が容易になります。紙の請求書では、保管スペースの確保や長期間の保管が必要ですが、電子請求書であればデジタルデータとして効率的に管理でき、必要な情報を迅速に検索・参照することができます。これにより、経理担当者の業務負担が軽減され、より戦略的な業務に集中できる環境が整います。 -
環境負荷の軽減
また、請求書の電子化は、環境負荷の軽減にも貢献します。紙の使用量を減らすことで、森林資源の保護やCO2排出量の削減に寄与し、企業の社会的責任(CSR)の一端を担うことができます。持続可能な経営を実現するためにも、電子化は重要な取り組みとなります。
このように、物流業界における請求書の電子化は、コスト削減、業務効率化、環境保護など多くのメリットをもたらします。次に、請求書電子化を導入するための具体的なステップについて解説します。
請求書電子化を導入するまでの4つのステップ
請求書の電子化のメリットは理解できても、実際に導入する際の手順に悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは、請求書を電子化するための具体的な流れをわかりやすく解説します。
①現状の請求業務を分析する
まず、自社の請求業務を詳細に分析します。月間の請求書発行件数や作業にかかる時間、コストを算出し、紙の管理負担や郵送費、ミスの頻度を把握しましょう。これにより、どの部分が負担になっているかが明確になります。課題を抽出した後で、優先順位をつけることが重要です。
②電子請求書サービスの選定
次に、自社に最適な電子請求書サービスを選定します。必要な機能を備えているかはもちろん、電子帳簿保存法やインボイスなどの法的要件に対応しているかどうかを確認します。また、社内のITリテラシーを考慮し、適切なサポート体制があるサービスを選ぶことが、スムーズな導入に繋がります。
③社内体制の整備
電子化に伴い業務フローが変更されるため、関係部門と情報を共有し、新たな運用ルールを策定します。業務マニュアルを作成して標準化を図り、社員間で共通認識を持つと、導入後の運用を安定させやすくなります。
④試験運用
本格的な導入前に、限定的な範囲で試験運用を行い、実際の業務にどれだけ適応できるかを確認します。
たとえば、一部の取引先や業務に限定して試験運用を実施し、課題を洗い出します。試験運用に問題がないことを確認してから本格導入に移行することで、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。
請求書電子化サービスを選ぶ際のチェックポイント
請求書の電子化を成功させるためには、自社に最適なサービスを選ぶことが不可欠です。市場には多くの電子請求書サービスがあり、導入後に「期待していた効果が得られなかった」「サポートが不十分だった」などの問題が発生することもあります。そこで、サービス選定時に必ず確認すべきポイントを解説します。
①業務に必要な機能が揃っているか
電子請求書サービスにはさまざまな機能があり、企業によって必要な機能も異なります。導入前に、自社の請求業務のフローを整理したうえで、必要な機能が備わっているかを確認することが大切です。
主なチェックポイントをご紹介します。
- 請求書の自動作成・送信機能:手作業の負担を減らし、ミスを削減できるか。
- 取引先とのデータ連携:取引先が異なるフォーマットを求めた場合に対応できるか。
- 検索・管理機能:過去の請求書をすぐに検索・確認できるか。
- 会計ソフトやERPとの連携:既存のシステムとスムーズに連携できるか。
- 承認フローの設定:社内のワークフローに適合しているか。
②どの程度の導入効果が見込めるか
システム導入の目的は、業務効率化とコスト削減です。導入することで、どれくらいの効果が見込めるのかを事前に試算することが重要になります。
導入前に試算すべきポイントをご紹介します。
- 削減できる作業時間(請求書発行・送付・管理にかかる時間の短縮)
- 削減できるコスト(紙・印刷・郵送費用の削減)
- ヒューマンエラーの防止効果(入力ミスや送付漏れの削減)
導入前にデモンストレーションや具体的なコスト削減効果に関する相談ができるサービスもあるため、試用して効果を確認するのも有効です。
③サポート体制が自社に合っているか
電子請求書サービスは、導入後も継続的な運用が必要になります。そのため、システムを提供する会社のサポート体制が十分かどうかも重要なポイントです。
確認すべきサポート内容をご紹介します。
- 導入時のサポート:設定や社内展開を支援してくれるか。
- トラブル対応:エラー発生時に迅速な対応が可能か。
- ヘルプデスクの対応時間:24時間対応なのか、平日限定なのか。
- マニュアルやFAQの充実度:利用者向けのドキュメントが整備されているか。
特に、電子帳簿保存法やインボイス制度に関する問い合わせに対応しているかどうかも、選定のポイントになります。法改正があった際に、サービス側が適切にアップデート対応をしてくれるかどうかは、長期的な運用を考える上で重要です。
また、取引先が請求書の電子化に不慣れな場合、サポート体制が整っていないと、取引先との調整が難航することもあります。導入時に取引先とスムーズに連携できるよう、サポート内容を事前に確認しておきましょう。
④電子帳簿保存法やインボイス制度への対応可否
日本では電子帳簿保存法(電子データでの請求書保存に関する法律)や、インボイス制度(適格請求書発行事業者の登録制度)が適用されており、これらの法規制に対応したサービスを選ぶことが必須です。
電子帳簿保存法への対応
電子請求書は電子帳簿保存法に則った形式で保存する必要があり、対応していないシステムを選んでしまうと法的に無効な請求書となります。
電子帳簿保存法が求める要件を満たす製品にはJIIMA認証(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)のロゴが付与され、法令に準拠した処理を行うことができます。
インボイス制度への対応
2023年10月から始まったインボイス制度では、適格請求書の発行が義務付けられています。たとえば、適格請求書の発行ができないサービスを導入してしまうと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、取引に支障が出る可能性があります。導入前に必ず法対応の有無を確認しましょう。
請求書電子配信サービス「bizform online 配信」

キヤノンマーケティングジャパンでは、請求書電子配信サービス「bizform online 配信」を提供しています。請求書を電子化することで物流業界の業務がどのように変わるのか、bizform online 配信でできることを解説します。
紙・印刷・郵送費などのコスト削減
請求書の発行にかかるコストは、単に「印刷代」と「郵送代」だけではありません。紙の請求書を発行するためには、次のようなコストも発生します。
- 印刷コスト:用紙代、プリンターのインク代
- 封入作業の人件費:手作業で封入・封かんする時間
- 郵送コスト:切手代・宅配便代
- 保管コスト:書類のファイリング・収納スペースの確保
- 管理コスト:請求書の検索・確認にかかる時間
また、2024年秋からは郵便料金が約30%値上げされました。たとえば、これまで1ヶ月に1000通の請求書を発行する企業の場合、郵便料金だけで年間コストが31万2,000円ほども増加します。さらに、請求書の処理にかかる人件費や、紛失・再発行の手間を考えると、その負担はさらに大きくなるでしょう。
bizform online 配信を導入することで、年間3,000通の請求書を電子化した場合、従来744万円かかっていたコストが221万円にまで抑えられた事例もあります。請求書の電子化は単なるデジタル化ではなく、「コスト最適化戦略」の一環としても非常に有効です。
請求書に付随する書類が添付可能に
物流業界の請求業務では、単に請求書を発行するだけでなく、次のような関連書類の添付が必要になるケースが多々あります。
- 納品書・受領書(納品の証明として取引先へ送付)
- 運送伝票(貨物の輸送に関する詳細情報)
- 契約書・見積書(特定の取引条件を確認するための書類)
紙の請求書では、これらの書類を別々に送付する必要があり、管理が煩雑になりがちです。また、書類を紛失した場合、再発行の手続きが発生し、余計な業務が発生してしまいます。
bizform online 配信は請求書だけではなく、あらゆる書類を電子化できます。自社や取引先独自のフォーマットなど現在のフォーマットを変えることなく対応可能です。また、取引先の部署ごとに閲覧したい書類が異なる場合でも、帳票ごとに利用者の閲覧範囲を制御できます。さらに、本社一括配信だけでなく、支店ごとなどの配信にも対応可能です。発行元ユーザーごとに配信・閲覧の権限を設定でき、組織の運用体制に合わせた柔軟な管理が実現できます。その結果、取引先とのやり取りのスピードが向上し、請求処理の利便性や正確性も大幅に向上することが期待できるでしょう。
担当者の業務負担の軽減
物流業界の経理担当者は、毎月多くのの請求書を処理する必要があり、それに付随して以下のように膨大な関連業務が発生します。
- 請求書の作成・発行
- 取引先への送付(紙の場合は郵送手配)
- 入金管理・未回収リストの作成
- 取引先からの問い合わせ対応
これらを手作業で実施している場合、ヒューマンエラーが発生しやすく、ミスを修正するための時間も発生してしまいます。bizform online 配信では以下のような機能によって、経理担当者の業務負担軽減に寄与します。
- 既存システムから自動連携でデータをアップロード。請求書をすぐに取引先へ送付が可能です。請求書が配信されると得意先に自動でメール通知。送付の手間を大幅に削減します。
- PDFデータの分割&名寄せ、データ抽出といった高度なデータ連携処理にも対応。さらに紙の請求書をご希望の取引先へは、オプションで印刷・封入・郵送を代行します。
- 属人化を防ぎ、誰でも業務を遂行できる体制を構築できます。
bizform online 配信は物流業界の経理担当のみなさまの負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を生み出します。
請求書を電子化し、業務効率化に取り組む企業の事例
ここまで、物流業界が業務効率化を進めるための一歩として、請求書の電子化が有効であることを解説してきました。では、請求書の電子化に先行して取り組んだ企業では実際に効果は出ているのでしょうか。具体的な事例をご紹介します。
日本通運株式会社
日本通運株式会社では月に7万5,000件の請求書を発行しており、紙での発行には印刷、封入、営業担当者による直接の持参など、多くの時間と労力を費やしていました。経営計画の目標のひとつでもあった後方事務の省力化や効率化を実施するにあたり、請求書発行業務の改善がスタート。
もともと月間約2万件も請求書を発行していた陸上輸送部門に「bizform online 配信」を導入した結果、導入から2年ほどで発行件数が約1万件にまで半減しました。受取企業からも、即日請求書の内容確認ができるようになったことや、紙の請求書にかかっていたコストや手間を削減できたことから高評価を得られています。さらに、請求書を電子化することでペーパーレス化を推進し、物流企業としてカーボンオフセットの取り組みにも貢献できるようになりました。
まとめ
物流業界において請求書の電子化は、コスト削減や経理担当者の業務負担軽減など多くのメリットが享受できるため、業務効率化の手段として非常に有効です。Webでの配信により郵送よりも早く、長期保存も容易になるため、受取先企業とのやりとりもよりスムーズになります。
キヤノンマーケティングジャパンの請求書電子配信サービス「bizform online 配信」は、現在の請求書フォーマットを変えることなく電子化ができます。紙の請求書からの手間を最小限に抑え、あらゆるシステムとも柔軟な連携が可能です。
具体的なコスト削減効果を試算できるシミュレーションもございますので、お気軽にお問い合わせください。
※ 月間通数1,000通以上の運用をされる企業さまに最適なサービスです。
導入事例
こちらの記事もおすすめです
「BPOソリューション」についてのご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BPO企画部