従来型セキュリティの限界を超える:ゼロトラストセキュリティが実現する新時代の防御中堅・中小企業も待ったなし!
公開日:2025年10月14日

クラウドサービスとリモートワークが業務の中心になった今、社内と社外の境界をファイアウォールだけで守る従来型セキュリティモデルは限界に達しています。働き方は多様化し、従業員は自宅や出張先から直接SaaSへアクセスするのが当たり前になった現在、社内外の境界は事実上消滅したとする見方もあります。
その空白を埋める新しい防御モデルとしてゼロトラストが急速に台頭しています。
本記事では、ゼロトラストの考え方を理解し、「準備→導入→運用→改善」というロードマップに沿って実践するための要点をまとめました。
従来型セキュリティモデルの限界
従来型モデルの最大の特徴は、信頼する内部ネットワークを前提にした“境界依存”の設計です。
社内ネットワークとインターネットの間に防御線を設ける従来型セキュリティは、企業成長を支えてきた実績があります。
しかし、クラウド、モバイル、SaaSといった利用形態が当たり前となった現在、その防御線は物理的にも論理的にも曖昧になりました。
守るべき対象がデータセンター内のサーバーからクラウド上のアプリケーション、さらには従業員の自宅ネットワークまで広がった以上、「どこが社内か」を定義すること自体が困難です。この構造的な限界を認識しないまま新しいサービスやデバイスを追加すると、統制が取れずセキュリティコストだけが雪だるま式に膨れ上がります。
中堅・中小企業がゼロトラスト導入を急ぐべき理由
攻撃者はセキュリティ投資が潤沢な大企業よりも、防御が手薄な中堅・中小企業を狙う傾向を強めています。
IPAが発表した2024年の統計では、サプライチェーン攻撃の被害企業の63%が従業員300名未満でした。パッチ適用が遅れやすい環境が攻撃者の格好の餌食になっています。
一方で、中堅企業ほどクラウドやSaaSを積極活用してコストを最適化しています。
自社でたくさんの機器を持つよりも、クラウドサービスを使って「誰が」「何に」アクセスできるかを管理する方が、費用を抑えつつ、会社の情報をもっと安全に守れるようになるからです。
ただし一気に全社導入するのは現実的ではありません。段階的導入というキーワードを念頭に、スコープを広げていく進め方が推奨されます。
ゼロトラストセキュリティとは
ゼロトラストセキュリティは「何も信頼しない」を前提に、すべての通信を都度検証することでリスクを最小化するアプローチです。
従来の境界型セキュリティでは対応しきれないクラウドサービスやテレワークの普及により曖昧になったネットワーク内外の脅威に対し、ユーザーやデバイスなど個別要素ごとにセキュリティ評価を行い、アクセス権を最小限に絞ることで攻撃の横展開を防ぎます。
これは単なる技術導入に留まらず、動的なポリシー適用、継続的な可視化と監査、インシデント対応の自動化を含め、サイバー攻撃の発生を前提に「被害を素早く限定する」運用への転換を促すものです。
| 比較項目 | 従来型セキュリティ | ゼロトラストセキュリティ |
|---|---|---|
| 信頼の前提 | 社内は信頼 | 誰も信頼しない |
| アクセス管理 | 一度認証すれば自由 | 常に認証・検証 |
| 境界の考え方 | 社内と社外の境界 | 境界を設けない |
キヤノンMJグループで実施しているゼロトラストネットワークへの取り組み
キヤノンMJグループは、情報セキュリティ対策として物理的およびサイバーセキュリティの両面から取り組んでいます。
具体的には、入退室管理システムやESETセキュリティソリューション、情報漏えい対策ソリューションを導入・運用し、グループ全体の情報セキュリティレベルの向上を図っています。
これにより、安全な情報環境を維持し、リスクを最小限に抑えています。
ゼロトラストセキュリティ 7つの原則
業種や規模を問わず、多くの組織がサイバーセキュリティ対策のガイドラインとして、NIST(米国国立標準技術研究所)のCSF(サイバーセキュリティフレームワーク)を参考にしています。
このCSFの下位概念に位置づけられるドキュメント類の一つに「ゼロトラスト・アーキテクチャ」が存在します。
ゼロトラスト・アーキテクチャは、従来のセキュリティモデルとは異なり、「信頼しない、常に検証する」という原則に基づいています。
ゼロトラストの実装においては、以下の7つの基本的な考え方が重要とされています。
| ゼロトラスト 7つの原則 | 要約 | 代表的な要素 | |
|---|---|---|---|
| 1 | すべてのデータソースとコンピューティングサービスをリソースとみなす | 保護すべき情報資産を把握する | IT資産管理 |
| 2 | ネットワークの場所に関係なく、すべての通信を保護する | 社内や自宅、外出先など、場所にかかわらず、すべての通信を保護する | SASE |
| 3 | 企業リソースへのアクセスをセッション単位で許可する | リソースに対する必要最小限の権限を付与する | |
| 4 | リソースへのアクセスは、動的ポリシーにより決定する | リソースへのアクセスはリクエストごとに許可する | |
| 5 | すべての資産の整合性とセキュリティ動作を監視し、測定する | デバイスのセキュリティ状態を維持・監視する | EDR |
| 6 | すべてのリソースの認証と認可を⾏い、アクセスが許可される前に厳格に実施する | リソースに対する必要最小限の権限を付与する | IDaaS |
| 7 | 資産、インフラ、通信の現状について情報を収集し、セキュリティ態勢の改善に利⽤する | ログ情報を収集・分析して、セキュリティ対策の改善に利用する | SIEM |
ゼロトラストセキュリティの導入の5つのフェーズ
ゼロトラストの導入は、単なるセキュリティ強化に留まらず、業務効率の向上やコスト削減にも繋がるため、組織全体のIT戦略として捉えることが重要です。しかし、「どこから手をつければいいのか分からない」という声も少なくありません。
この章では、ゼロトラストセキュリティを効果的に導入するための具体的な5つのフェーズを解説します。
フェーズ1現状を把握し、理想の姿を描く(As-is分析、ありたい姿の検討)
- 何をするか
- ゼロトラスト導入の「目的」を明確にすることから始めます。現在のITシステムやセキュリティ体制の課題点(As-is)を詳細に洗い出し、同時に、将来的に「どんな状態を目指したいのか」(ありたい姿)を具体的に描きます。
- ポイント
- セキュリティの観点だけでなく、社員の使いやすさ(ユーザー利便性)やシステム運用の効率性も考慮に入れることが重要です。漠然とした目標では、期待する効果は得られません。経営層をはじめ、各部署の関係者との対話を通じて、組織全体の課題と目標を共有しましょう。
フェーズ2具体的な設計図を作る(グランドデザイン作成)
- 何をするか
- フェーズ1で描いた理想の姿を実現するための具体的なシステム構成や、導入すべきセキュリティソリューションを検討し、詳細な設計図(グランドデザイン)を作成します。
- ポイント
- 現状(As-is)と理想(ありたい姿)のギャップを埋めるための具体的な導入計画を策定します。特に、誰がどこまでアクセスできるかを管理する「ID管理」や、社内デバイスを適切に管理する「デバイス管理」など、ゼロトラストの基盤となる部分から優先的に着手することが成功への近道です。
フェーズ3導入の価値を評価し、意思決定する(投資判断)
- 何をするか
- 作成したグランドデザインに基づき、導入にかかるコストだけでなく、それによって得られるセキュリティ強化、ユーザー利便性の向上、運用効率化といった幅広い効果を評価します。これらの情報を経営層や関係者に提示し、導入の承認を得ます。
- ポイント
- 「もし対策をしなかったらどんなリスクがあるか」という脅威だけでなく、「ゼロトラストによって組織がどう進化できるか」という前向きな視点から、組織全体にもたらす価値を具体的に説明することが大切です。
フェーズ4計画に基づきシステムを構築する(環境構築)
- 何をするか
- フェーズ2で作成したグランドデザインと、フェーズ3で承認された計画に基づき、実際に必要なセキュリティツールやシステムを導入し、ゼロトラスト環境を構築します。
- ポイント
- 最初から全てを変えるのではなく、まずは一部の部署やシステムで試行し、問題がなければ徐々に適用範囲を広げていく「スモールスタート」のアプローチが効果的です。これにより、リスクを抑えつつスムーズな移行を進めることができます。
フェーズ5効果を検証し、継続的に改善する(検証・改善)
- 何をするか
- 導入したシステムが期待通りの効果を出しているか定期的に検証し、アクセスログの監視などを通じて不審な動きを早期に発見・対処できる体制を構築します。
- ポイント
- ゼロトラストは一度導入したら終わりではありません。常に変化するサイバー攻撃の脅威やビジネス環境に合わせて、定期的に見直しと改善を続けることが不可欠です。効果測定を行い、継続的なセキュリティ強化と運用最適化を目指しましょう。必要に応じて、外部の専門家からのアドバイスも活用することで、より強固な体制を築くことができます。
ゼロトラストは、単なるセキュリティ対策ではなく、組織全体のIT戦略として、社員の働き方やビジネスのあり方を変革する可能性を秘めています。
これらの取り組みを計画的に進めることで、より安全で効率的なビジネス環境を整え、企業の持続的な成長を支える強固な基盤を築くことができるでしょう。
まとめ
ゼロトラストは「信頼を前提にしない」というシンプルな原理で、従来型セキュリティが抱えていた構造的な限界を打ち破ります。
社内への侵入後のマルウエアの広がり、会社が知らないITサービス(シャドーIT)からの情報漏えい、そしてリモートワークやクラウド利用で会社の機器やデータが社外に散らばったことで、誰がどこから安全にアクセスしているか分かりにくくなるといった課題は、企業の規模に関わらず顕在化しています。
ゼロトラストを成功させる鍵は技術選定よりも「どの資産を守り、誰がどのようにアクセスするのか」というビジネス要件の明確化にあります。
「何も信頼しない」というゼロトラストの考え方を基本に、「必要なものだけにアクセスを許可し、状況に応じてルールを変え、常に監視する」という3つの大事な考え方を軸に、様々な最新技術を組み合わせることで、クラウドの活用や、どこからでも働く(テレワークなど)ような新しい働き方に合わせた、柔軟な防御態勢を構築できます。
最後に、ゼロトラストは一度導入したら終わりではなく、常に改善を続けていくものです。
実際に試してわかったこと(例えば、どれくらい安全になったか、どこに課題があるかなど)をデータとして残し、専門家による模擬攻撃訓練や自動でチェックする仕組みを使って、常にセキュリティ対策を改善し続けられます。
これにより、どんな新しい脅威にも素早く対応できる、盤石なセキュリティ体制を築いていきましょう。
アドバイザー:サイバーセキュリティラボ(キヤノンITソリューションズ株式会社)
セキュリティラボでは、サイバーセキュリティに関する調査・研究・情報発信しています。
事業活動にとどまらず、国内外のトレンド調査、大学との共同研究などに取り組むほか、学会での論文発表、「サイバーセキュリティ情報局」での情報発信などを通じて、知見・ノウハウを世の中に広く伝える活動にも注力しています。
高度な脅威に対抗するソリューション
キヤノンマーケティングジャパングループでは、ゼロトラストに関する要素を備えた、高度な脅威に対抗するソリューションを体系的にご用意しています。
グループで長年にわたり蓄積してきたサイバーセキュリティ対策のノウハウや経験を活かして、具体的な課題への対策と、ゼロトラストの段階的な導入を支援します。
サイバーセキュリティ対策の継続的改善や高度化に向けて、お客さまの環境に適したセキュリティソリューションをご提供します。
外部脅威への対策
内部脅威への対策
運用管理の対策
今知っておくべきサイバーセキュリティ対策
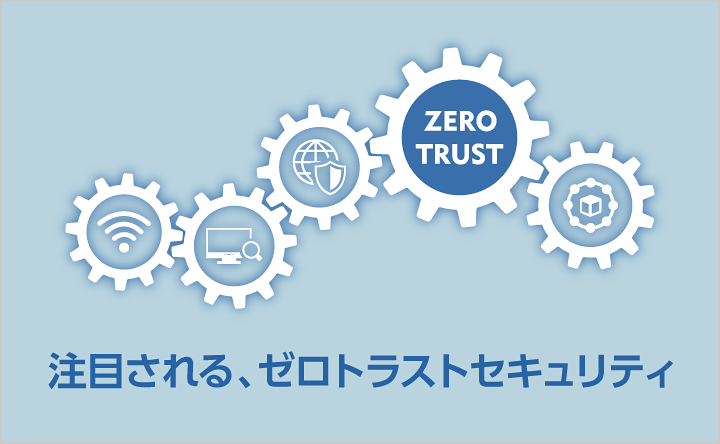
企業の信頼を守るために、今知っておくべきサイバーセキュリティ対策について、詳しくまとめました。
















