【ヘルプデスクの効率化対策4選】これで問い合わせ対応の負担からの解放を目指す!
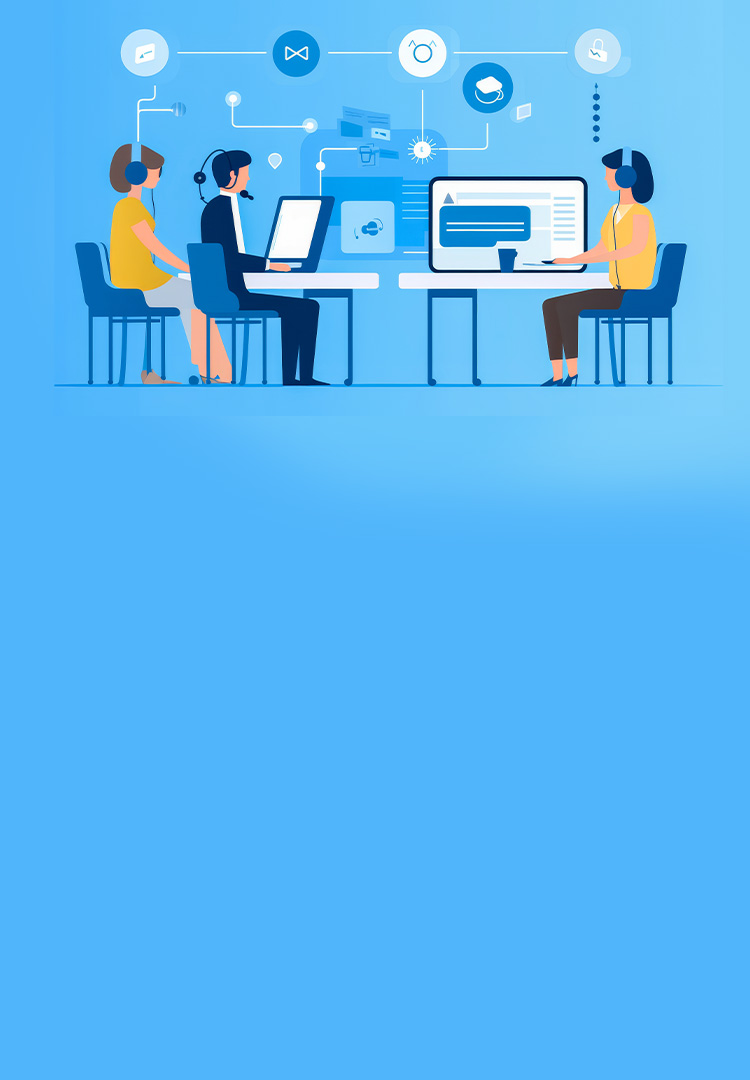
業務効率化やDX化が推進される今、あらゆる企業でITデバイスやITシステムの導入が盛んに行われています。それに伴いヘルプデスクの業務量も増加傾向にあり、「問い合わせが多くてコア業務に集中できない」などの課題を抱えるヘルプデスク担当者が多いのが現状です。そこで本記事では、「社内ヘルプデスク」に焦点をあて、ヘルプデスクの課題や効率化を図るための具体的な方法について詳しく解説します。
公開日:2025年8月6日
目次
- ヘルプデスク業務とは
-
ヘルプデスク業務が抱える課題
- (1)問い合わせが多い・減らない
- (2)属人化しがちである
- (3)従業員満足度が低い
- (4)繁閑がある
- (5)そもそも人材が不足している
- (6)業務効率化に手が回らない
- ヘルプデスク業務の効率化を進める方法4選
- ①問い合わせ数を減らす
- ②属人化を排除する工夫をする
- ③応対品質を評価する
- ④アウトソーシングを活用する
- まとめ
ヘルプデスク業務とは

ヘルプデスクには、顧客や取引先の問い合わせに対応する社外ヘルプデスクと、従業員からの問い合わせに対応する社内ヘルプデスクの2種類があります。このうち本記事では、後者の社内ヘルプデスク(以下、ヘルプデスク)をテーマに解説します。
ヘルプデスクとは、ITデバイスやシステムを使用する従業員の質問や疑問に答えたり、トラブルシューティングを行ったりする業務を指します。寄せられる問い合わせは多岐にわたり、パソコンやOA機器の設定・操作に関すること、ネットワーク接続に関すること、導入したシステムの操作や運用に関することなどさまざまです。このほか、機材調達やアカウント管理、ソフトウェア管理なども含まれます。
そのためヘルプデスク担当者には、各種デバイスやネットワーク、システムに関する幅広い知識・技術が求められます。また、配属部門については、大きな組織であれば社内ヘルプデスク専門の部署が設置されることもありますが、情報システム部や総務などが兼務するケースが一般的です。ヘルプデスクが正常に機能することで、企業活動が円滑に進むだけでなく、従業員満足度の向上が期待できます。
ヘルプデスク業務が抱える課題
ヘルプデスクは企業において重要な役割を担いますが、改善すべき課題が多いのも特徴です。ここでは、ヘルプデスクが直面しやすい課題を6つ解説します。
(1)問い合わせが多い・減らない
ヘルプデスクが抱える課題のひとつに業務過多が挙げられます。その大きな要因となっているのが、問い合わせ件数の多さです。組織の業務効率化や生産性向上を目指し、各種ITデバイスやクラウドシステムなどを導入する企業は増えています。
使うデバイスやシステムが増えれば、その操作方法やエラー時の対処方法など、ヘルプデスクに寄せられる問い合わせもおのずと増えてしまいます。たとえば「アプリケーションをインストールできない」「新入社員のパソコンをセットアップしてほしい」「導入したシステムの操作方法がわからない」などです。企業によっては、周りの人に聞いたり共有資料を確認したりすれば解決できる問題を、一手にヘルプデスクが引き受けているケースも見られます。
(2)属人化しがちである
ヘルプデスクの対応範囲が広くなるにつれ、部門内でナレッジの共有がうまくされず、対応が属人化してしまうケースも多々見られます。属人化によって業務が集中すれば特定の人員の負担が増え、長時間労働が常態化し、担当者の休職や離職を招く恐れがあります。
休職や離職によって人材が不足すれば、人あたりの業務量は増大し、さらなる長時間労働や離職を招く要因に。ヘルプデスクに限らず専門性が必要な部門は属人化しがちな傾向にあるため、今はまだナレッジの共有ができている場合も十分な注意が必要です。
(3)従業員満足度が低い
従業員の困りごとを解決するヘルプデスクは、迅速な対応が不可欠です。しかし、先述のように問い合わせが多かったり、業務が属人化していたりすると、対応が後手に回ってしまうことがあります。
ヘルプデスクの対応が遅れると、社内の業務が滞り業務効率が低下し、結果として従業員満足度の低下につながります。「ヘルプデスクに問い合わせてもすぐに対応してくれない」などの声が上がっている場合は、早急に対処する必要があるでしょう。
(4)繁閑がある
繁閑対応が困難な点もヘルプデスクが抱える課題のひとつです。ヘルプデスク業務は、新システムの導入時、年度の切り替わり時、パソコンの入れ替え時に問い合わせが増える傾向にあります。しかし、繁忙時に合わせて人員を配置できる企業ばかりではありません。一時的にでも生まれる人材不足は業務過多を招き、ヘルプデスクの負担を増大させる要因となります。
(5)そもそも人材が不足している
繁忙時に限らず、通常時においてもヘルプデスクの人材が不足しているケースも珍しくありません。ヘルプデスク業務をその他のバックオフィス部門の人材が兼務している場合は、特にその傾向が見られます。
社内のヘルプデスクのニーズは高まりを見せているものの、売上に直接結びつかない間接部門であることから、十分な人材リソースを割けないというのが企業の実状。このようなケースでは、少ない人員でいかに効率的に業務を回すかが鍵となります。
(6)業務効率化に手が回らない
ヘルプデスク部門の業務効率化の必要性は理解していても、日々の業務に追われ、改善活動が思うように進まないケースも少なくありません。しかし、これまで見てきたとおり、ヘルプデスク業務の最適化は組織全体の業務効率や生産性の向上、従業員満足度の向上につながる重要な取り組みです。以降で紹介する「ヘルプデスク業務の効率化を進める方法」を参考に、できることから着手していくことが大切です。
ヘルプデスク業務の効率化を進める方法4選

ここからは、ヘルプデスクの業務を効率化する方法を4つ紹介します。
- 問い合わせ数を減らす
- 属人化を排除する工夫をする
- 応対品質を評価する
- アウトソーシングを活用する
それぞれの詳細や手順を詳しく見てみましょう。
①問い合わせ数を減らす
そもそもの問い合わせ数を減らす方法です。ポイントは「従業員の自己解決を促す仕組みづくり」にあります。ヘルプデスクに寄せられる問い合わせには、初歩的な質問や容易に解決できる問題が含まれていることが多く、これらにヘルプデスク部門が人的リソースを割いて対応するのは非効率だといえます。
FAQやチャットボットなど、従業員が自己解決できる機能を設置すれば、ヘルプデスクに寄せられる問い合わせ件数が減り、業務の効率化が進みます。具体的な手順は次のとおりです。
対応範囲を明確にする
まずは、ヘルプデスクが対応すべき範囲を明確にします。ヘルプデスクに蓄積された問い合わせ内容を、「ヘルプデスク担当者が対応しなければ解決しないもの」と「ヘルプデスク担当者が対応しなくても解決できるもの」に分類してみましょう。
FAQを設置する
「ヘルプデスク担当者が対応せずとも解決するもの」の中から、問い合わせ頻度の高いものをFAQ(よくある質問)にまとめます。回答文は専門用語を避け、誰もがわかる言葉を用いるのがポイントです。
FAQは紙ではなく、共有しやすく分析可能なWeb展開が有効です。Webページの作成は、FAQシステムを導入するとスムーズに実装できます。システムにはタブや検索機能があるため、ユーザー自らが求める情報を探し、得たい回答を取得するのが特徴です。また、画像や動画なども掲載できるため、言葉だけでは伝えにくい回答にも適しています。
さらに、FAQシステムの内容を定期的に更新すれば、ヘルプデスク業務のナレッジの一元管理にも役立ちます。
チャットボットを導入する
FAQとあわせて導入を検討したいのがチャットボットです。トーク画面に質問を入力すると、それに適した回答を瞬時に表示してくれます。FAQシステムと異なりユーザー自身で情報を探す手間がかからないため、より効率的に回答を得ることができます。ただし、チャットボットはLINEなどのチャットアプリと同様、長文テキストの可読性は高くありません。そのため、複雑な回答が求められるケースには不向きです。
一度に多くの情報を提示したい場合はFAQシステム、簡潔に表示できる場合はチャットボットという使い分けを意識するといいでしょう。ただし、チャットボットでも、別ページに遷移させることで情報を補うことは可能です。なお、チャットボットにはAI搭載型とAI非搭載型があり、それぞれ機能や費用が異なります。自社に合った運用を検討してみてください。
FAQやチャットボットの活用を促す
FAQやチャットボットを導入したら、社内周知が必須です。せっかく導入しても活用されなければ、本来の目的であるヘルプデスクの業務効率化は達成されません。ヘルプデスクに問い合わせる前に、「FAQあるいはチャットボットを利用する」という習慣を身につけてもらうことが大事です。周知の際には、時間の制限なく利用できる点など、従業員へのメリットを提示しながら行うとよいでしょう。

チャットボットとの連携による自己解決型ヘルプデスク活用でサポート品質の向上を図るとともにIT部門の負担軽減を実現
②属人化を排除する工夫をする
ヘルプデスク業務の属人化を改善するときは、ナレッジを共有し、業務を標準化する必要があります。
主な方法は次のとおりです。
対応マニュアルを作る
従業員が使うデバイスやシステムが多様化するなか、ヘルプデスクに求められる知識も広範囲に及びます。寄せられた問い合わせに対して誰もが適切に対応できるようにするためには、ノウハウの明文化と共有が欠かせません。そこで役立つのがマニュアルです。
手順としては、質問・回答・従業員の反応をテキストに起こし、内容ごとにカテゴライズします。マニュアルツールを使用すれば検索もスムーズです。解決方法だけでなく、説明の仕方や言葉遣いなども集約すると、より実務で役立ちます。マニュアルはノウハウの蓄積場所という側面もあるため、少しずつでも着手することをおすすめします。
問い合わせ管理システムを導入する
属人化によって対応に遅延が発生している場合は、問い合わせ内容や対応の進捗などをリアルタイムで共有できる「問い合わせ管理システム」の導入が有効です。
問い合わせ管理システムとは、ヘルプデスクやコールセンターの業務効率化に特化したシステムのこと。問い合わせ管理システムを使えば、問い合わせ内容や進捗の一元管理が可能となり、ヘルプデスク業務をチームで対処しやすくなります。また、データが蓄積されることで、問い合わせ内容の傾向やボトルネックの分析も可能になります。
回答のテンプレートを作成する
マニュアルや管理システムを導入すると、問い合わせ内容の傾向が可視化され、いくつか類似した質問・回答があることがわかります。そのうち、定型的な対応が可能なものについては回答のテンプレート化を進めていきましょう。テンプレート化することで、誰が担当しても一定の品質を保ちやすくなります。従業員満足度の向上が期待できるとともに、業務効率もアップします。
③応対品質を評価する
業務効率化は、業務プロセスに生じる「ムリ・ムダ・ムラ」を省き、限られたリソースを最大限活用することで実現します。担当者によって対応にバラつき(ムラ)がある場合は、応対品質を評価し、教育内容の見直しを進めていきましょう。適切な評価と教育は、ヘルプデスク担当者の離職や休職を防ぐことにもつながります。
具体的な手順は以下のとおりです。
改善すべき点を把握する
応対品質を評価するにあたり、まずは現状の把握が不可欠です。ヘルプデスク部門内で情報を収集するともに、従業員に向けてオンラインアンケートを実施するなどして、ユーザー視点の意見も吸い上げましょう。ヘルプデスクのメンバー間では気づけない改善点が見つかることがあります。
評価項目を設定して実施する
現状を把握したら、評価項目を設定し、担当者それぞれを評価します。ヘルプデスクは従業員の困りごとに迅速に対応し、業務効率化や生産性向上に寄与するとともに「何か困ったときに相談できる窓口がある」という安心感を与える役割も担っています。評価項目を設定する際は、これらを踏まえて行いましょう。
以下は評価項目の例です。
応対品質の評価項目例
- 正確性:情報は正確か
- 迅速性:スピーディに対応できているか
- 柔軟性:臨機応変に対応できているか
- 安心感:従業員が安心して相談できる雰囲気をつくれているか
評価のフィードバックを行う
面談を実施し、評価のフィードバックを行います。評価を受ける側は不安を抱えていることが多いため、威圧的な態度やマイナス要素を責めるような話し方は禁物です。適切なフィードバックは、部下のモチベーションを上げ、成長を促します。
教育内容を見直す
評価によって改善点が明確になったら、利用する従業員の指摘も取り入れながら教育内容を見直します。情報の正確性に欠けていたり、知識が不足していたりするときには、マニュアル等を充実させ、活用を促すことで改善するケースがあるでしょう。柔軟性や安心感に改善点がある場合は、コミュニケーション力を強化する教育を取り入れると効果的です。ロールプレイングや先輩のヘルプデスク担当者に直接指導してもらう機会をつくるといいでしょう。
④アウトソーシングを活用する
ヘルプデスク業務をアウトソーシングするのも有効な手段のひとつです。次のような場合には、特に高い効果が見込めます。
慢性的に人手不足に陥っている
業務改善には相応の人的リソースが必要です。しかし、ヘルプデスクの人材不足が常態化している場合、通常業務を滞りなく進めるのに手一杯で、業務改善に取り組む人員を確保できません。新規採用を試みても、ITスキルのある人材の需要は高いため叶わないケースも多く、たとえ採用できても教育する時間を取れないのが現状です。
このようなケースの場合、アウトソーシングの活用は有効な解決手段です。業務量に応じてヘルプデスク業務に精通した人材が、常に一定の応対品質で業務を遂行してくれます。
自己解決手段が用意されていない、または活用されていない
FAQやチャットボットなど、従業員が自ら疑問を解決できる仕組みが整っていないと、些細な問い合わせもすべてヘルプデスクに集中し、対応負荷が増大します。業務効率の低下を招くだけでなく、回答の遅延による従業員満足度の低下にもつながります。
アウトソーシングサービスの中には、蓄積された問い合わせデータをもとにFAQを構築したり、実際のやりとりに即したチャットボットのシナリオを作成したりと、自己解決の仕組みそのものを整備してくれるサービスもあります。業務効率化に必要な環境づくりを一括して任せられるのが大きなメリットです。
ナレッジ共有の仕組みがない
ヘルプデスク業務の効率化を実現させるためには、問い合わせ対応のノウハウや過去事例など、メンバー間のナレッジ共有が不可欠です。しかし、実際にはその仕組みを構築できていない企業は少なくありません。ヘルプデスク業務のアウトソーシングでは、対応履歴の管理や問い合わせ集計・分析などを通じてナレッジの可視化と共有を可能にし、効率的で満足度の高いヘルプデスクを実現します。
問い合わせ窓口が一本化されていない
ヘルプデスクの問い合わせ窓口が複数ある場合、ナレッジやノウハウもそれぞれの窓口に分散してしまいます。その結果、同じような問い合わせへの重複対応や、窓口ごとの対応品質のばらつきといった課題が生じやすくなります。こうした状況を自社内で整理・統合しようとしても、関係部署との調整やツール選定・運用設計などに多くの時間や工数がかかり、思うように改善が進まないケースも少なくありません。
このようなケースでも、アウトソーシングの活用が有効です。ヘルプデスク業務のプロが、ツールを活用した問い合わせ管理やナレッジ共有の仕組みを構築し、業務の標準化と効率化を推進します。
時間外対応が必要
企業の業種や業態によっては、労働時間外にヘルプデスク担当者の対応が必要なケースがあります。人員が十分であれば交替制勤務を採用することで対応できますが、人材が不足しがちなヘルプデスク業務では、実現が難しいケースがほとんどです。
このようなケースでは、外部拠点で対応を行う「オフサイト型」のアウトソーシングが効果的です。24時間体制の構築や、専門チームによる夜間対応など、自社だけでは実現が難しい時間外サポート体制を柔軟に構築できます。
まとめ
社内のIT関連の困りごとを一手に担うヘルプデスクは業務過多に陥りやすく、何らかの対策を施さなければ現場の負担は増える一方です。今後ますます業務IT化やDX化が進んでいく背景を考えると、ヘルプデスク部門の業務改善は早急に対処すべき課題といえます。
しかし、人的リソースが足らず、最初の一歩を踏み出せない企業も少なくありません。そうしたときに検討したいのが、業務の一部を外部に委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)です。「社内ヘルプデスクBPO」を活用すれば、業務の繁閑に左右されず一定レベルの応対品質を維持できるとともに、ヘルプデスク担当者が本来取り組むべき業務に専念できる環境づくりが可能になります。
私たちキヤノンマーケティングジャパングループは、お客さまのビジネス変革を、ITとBPOでご支援しています。BPOの活用方法や事例、効果などについて知りたいときは、お気軽にご相談、お問い合わせください。
関連ソリューション
こちらの記事もおすすめです
「BPOソリューション」についてのご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BPO企画部




