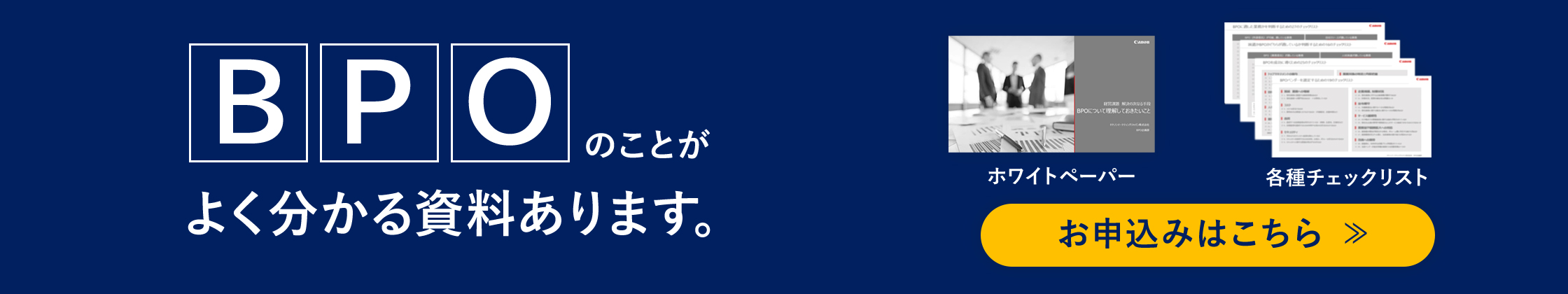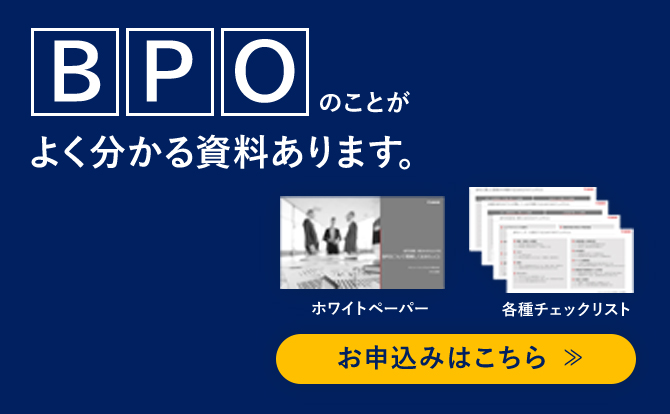BPM(ビジネスプロセスマネジメント)とは?導入メリットや具体的な活用方法を紹介

企業の競争環境が激しく変化する中、業務効率化やコスト削減がますます重要になっています。
そこで注目されているのが「BPM(ビジネスプロセスマネジメント)」という業務改善手法です。
この記事では、BPMの基本的な仕組みから導入のポイントまで、わかりやすく解説していきます。
公開日:2025年6月30日
目次
-
BPM(ビジネスプロセスマネジメント)とは?
- なぜ今、BPMが注目されているのか?
- BPMを導入する目的とは?
-
BPMと関連用語の違いや関係性とは?
- BPMとBPRの違い
- BPMとBPMS・BPMNの関係性
- ERPやワークフローシステムとの違い
-
BPMを導入するメリットとは?
- 業務プロセスの可視化が可能になる
- 業務課題の根本的な解決が図れる
- 組織全体のリスク回避につながる
-
BPMを導入するデメリットや注意点とは?
- 導入目的が曖昧だと効果が出にくい
- 現場からの協力や理解が不可欠
-
BPMの導入手順
- 手順1:業務プロセスの現状を可視化する
- 手順2:課題を特定し改善プロセスを設計する
- 手順3:改善プロセスの実施とモニタリングを行う
- 手順4:PDCAサイクルを継続して回す
-
BPMツール(BPMS)とはどのようなものか?
- 業務プロセスを設計・可視化するモデリング機能
- 業務の問題点を把握するシミュレーション機
- 業務改善の進捗を確認するモニタリング機能でPDCAを回せる
- 自社に適したBPMツールの選び方とは?
- まとめ|BPM導入で実現できることを再確認
BPM(ビジネスプロセスマネジメント)とは?
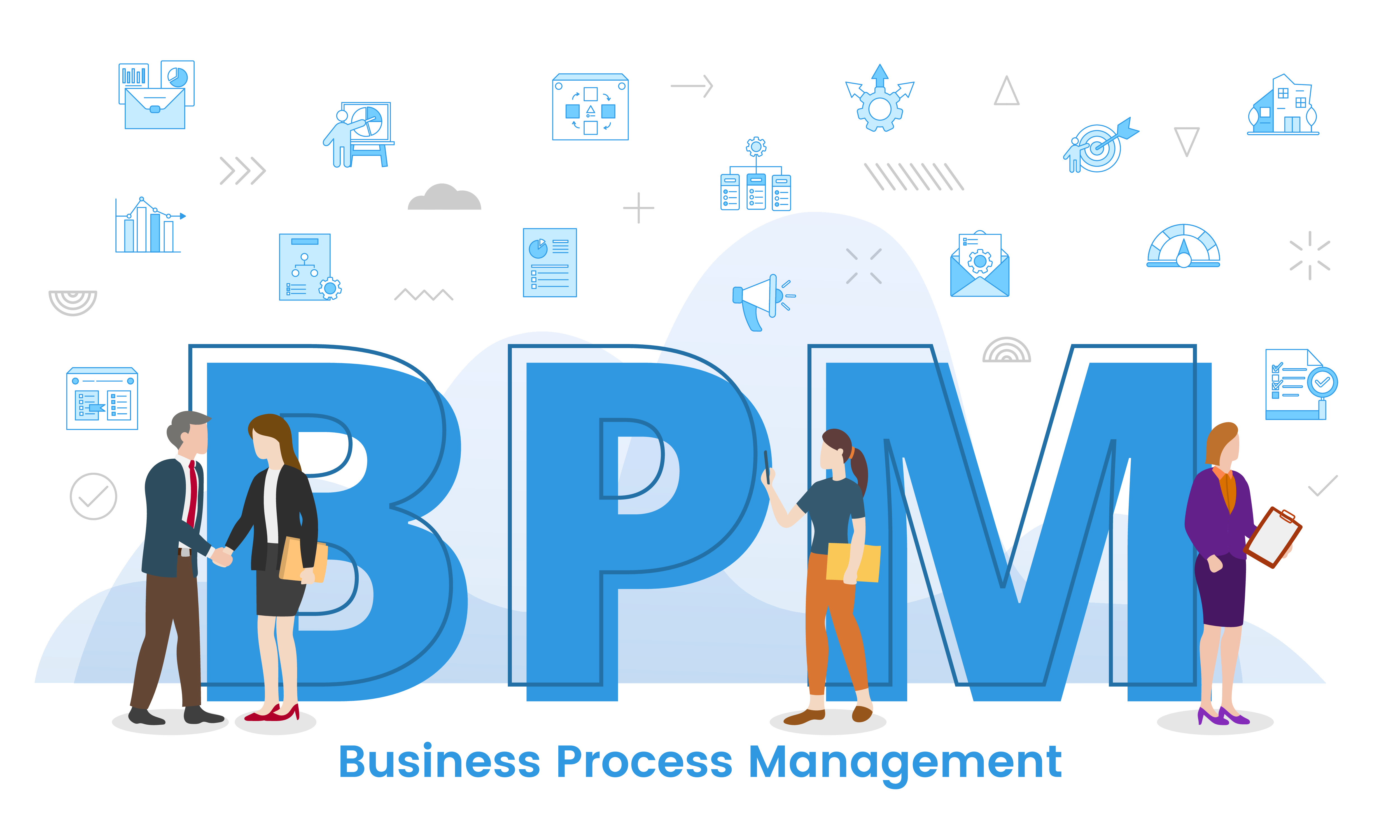
BPM(ビジネスプロセスマネジメント)とは、企業内の業務プロセスを整理し、継続的に改善していくマネジメント手法の一つです。具体的には、社内の業務フローを「見える化」して効率的なプロセスへと再構築し、それを組織全体で共有・管理します。
これまでの業務改善は、特定の部署やチームだけが個別に対応するケースが一般的でした。しかし、BPMでは企業全体の視点から業務プロセスを捉え、全社的な業務効率化や課題解決を推進していきます。そのため、部署をまたいだ課題も浮き彫りになり、抜本的な解決につながります。
また、BPMではPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を常に回していくことが重要です。一度プロセスを改善したら終わりではなく、継続的な改善活動を続けることで、常に最適な業務環境を維持できるのが特徴です。
なぜ今、BPMが注目されているのか?
近年、BPMが注目を集めている最大の理由は、企業を取り巻く環境が急速に変化しているためです。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)や働き方改革の流れを受けて、多くの企業が抜本的な業務改革を求められるようになりました。
また、市場競争が激化する中で、業務の効率化や生産性向上は企業にとって重要な課題となっています。従来型の場当たり的な改善では、現場の負担が増えるばかりで根本的な課題解決に至らず、業務が複雑化してしまいます。そこで、業務プロセス全体を俯瞰し、効率的に改善するBPMが支持されるようになりました。
さらに、コロナ禍以降、リモートワークや在宅勤務が増加し、業務の可視化や標準化が求められる場面が増えました。業務フローが明確になっていない状態では、在宅勤務中のコミュニケーションや業務連携に問題が生じます。そのため、業務の全体像を整理し、明確化するためのBPMの重要性が再認識されています。
BPMを導入する目的とは?
BPMを導入する主な目的は、業務効率化やコスト削減、さらには競争力強化を実現することです。具体的には、業務プロセスの可視化により、どこに問題があるのかを正確に把握し、無駄な作業や非効率なプロセスを削減できます。その結果、社員が本来注力すべき業務に集中でき、生産性の向上につながります。
また、業務プロセスを明確化することで、社員同士の共通認識を高め、業務の属人化を防ぐ効果もあります。これにより、組織全体のリスク管理がしやすくなり、トラブルやミスを未然に防止できるようになるでしょう。
さらに、継続的にプロセス改善を行うことで、市場変化や新たな課題にも迅速に対応できる組織体制が構築されます。結果として、自社の競争力を強化し、顧客満足度の向上にもつながるという大きなメリットがあります。
BPMと関連用語の違いや関係性とは?

BPMについて調べていると、似たような用語が多く登場します。しかし、似たように見えても、それぞれ異なる意味や目的があります。ここでは混同されやすい用語の違いや関係性について整理します。
BPMとBPRの違い
BPM(ビジネスプロセスマネジメント)とよく混同される用語に、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)があります。この二つの違いは、目的や取り組み方に明確に現れます。
BPRは業務プロセスをゼロベースで見直し、大胆に再構築することを目的としています。抜本的な改革を目指すため、一度に大きな変化を伴います。
一方、BPMは現状の業務プロセスを継続的に改善することに重きを置きます。小さな改善を繰り返しながら、着実に効率化を図っていく点が特徴です。
つまり、短期間で劇的な変化を求めるならBPRが適しており、日々の業務を継続的に改善し安定した成果を目指す場合はBPMが適しているのです。
BPMとBPMS・BPMNの関係性
BPMに関連する用語として、「BPMS」や「BPMN」もよく登場します。これらはBPMをより効率的に推進するために欠かせない要素です。
まず、BPMS(ビジネスプロセスマネジメントシステム)は、BPMの取り組みを支援する専用のソフトウェアです。業務プロセスの設計から実行、監視、改善までを一元管理することができます。BPMSを活用することで、業務の可視化や改善の進捗管理がスムーズになるのです。
また、BPMN(ビジネスプロセスモデリング表記法)は、業務プロセスを図式化するための国際的な標準記号です。業務の流れを誰でも理解できるように統一的なルールで表現するため、チーム間や部署間での意思疎通が容易になります。
つまり、BPMが業務改善の「概念や方法論」、BPMSがそれを実行するための「ツール」、BPMNがそれを分かりやすく「可視化するための表記法」と理解することができます。
ERPやワークフローシステムとの違い
ERPやワークフローシステムもBPMと混同されやすい用語ですが、それぞれ役割が異なります。
ERP(基幹業務システム)は、企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ)を一元管理するためのシステムです。財務会計や人事管理など、企業活動全体を支えることを目的としています。
ワークフローシステムは、書類の承認や業務の申請といった定型業務を電子化し、自動化するシステムです。業務の流れを簡素化・効率化しますが、改善活動のマネジメントまでは行いません。
BPMは、これらとは異なり、企業内の業務プロセスそのものを継続的に改善するための手法です。ERPやワークフローシステムを導入した後に、業務プロセスの継続的改善を実現するのがBPMの役割なのです。
BPMを導入するメリットとは?

BPMを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。特に業務の効率化や生産性の向上など、企業にとって具体的なメリットがあります。ここではその主なメリットについて詳しく解説します。
業務プロセスの可視化が可能になる
BPMを導入する最大のメリットは、業務プロセスの可視化ができる点です。どの業務がどのような流れで進められているのかを明確にすることで、業務の属人化を防ぐことができます。
また、業務プロセスが可視化されれば、非効率な業務や無駄な手順を容易に発見できます。その結果、業務の無駄を省き、作業効率が向上するのです。
さらに、新任者の業務習得期間を短縮し、社員全体の業務レベルの底上げにもつながります。
業務課題の根本的な解決が図れる
BPMは、業務の表面的な問題だけでなく、その根本的な原因まで踏み込んで解決することを目的としています。
業務プロセスを全体的に見直すことで、部署間の連携不足やコミュニケーションロスなど、見えにくかった問題点が浮き彫りになります。それらを一つずつ改善することで、繰り返し発生するトラブルやミスを防ぐことができます。
長期的に見れば、組織全体の競争力強化につながることが期待できます。
組織全体のリスク回避につながる
業務が可視化されると、リスク管理も容易になります。業務プロセスのどの段階にどのようなリスクが潜んでいるかを明確に把握できるため、予防策を講じやすくなるのです。
また、プロセスを明確にすることで、トラブルが発生した際の対応が迅速かつ適切になります。結果として、企業全体のリスク耐性が向上し、安定した経営基盤の構築に役立ちます。
BPMを導入するデメリットや注意点とは?
BPM導入には多くのメリットがありますが、注意すべき点も存在します。特に導入目的の曖昧さや現場の抵抗感など、導入前に知っておくべきデメリットや注意点について説明します。
導入目的が曖昧だと効果が出にくい
BPMを導入する際に最も注意すべき点は、導入目的を明確にすることです。何を改善したいのか、何を達成したいのかが曖昧なまま導入すると、活動が形骸化しやすくなります。
「コスト削減」「業務効率化」などの抽象的な目的だけでなく、具体的な数値目標を設定することで、改善活動が効果的に進むようになります。
現場からの協力や理解が不可欠
BPMは現場の理解と協力が不可欠です。トップダウンで導入を進めようとしても、現場が改善の必要性を理解していなければ、活動は定着しません。
業務プロセスを変更することに抵抗感を持つ社員もいます。そのため、導入前の説明会や研修を実施し、社員の意見を反映する場を設けることが重要です。
現場の意見を取り入れ、理解を深めることで、BPMの取り組みはよりスムーズに浸透します。
BPMの導入手順

実際にBPMを導入する際には、順序立てて進めることが重要です。適切な手順で進めることで、効率的かつ効果的な業務改善が可能になります。
導入の手順は下記の通りです。
| 手順 | 詳細 |
|---|---|
| 手順1 | 業務プロセスの現状を可視化する |
| 手順2 | 課題を特定し改善プロセスを設計する |
| 手順3 | 改善プロセスの実施とモニタリングを行う |
| 手順4 | PDCAサイクルを継続して回す |
ここからは具体的な導入手順を段階ごとに紹介します。
手順1:業務プロセスの現状を可視化する
最初に、自社の現状の業務プロセスを可視化することが重要です。「可視化」とは、業務がどのような流れで進んでいるのかを誰もがわかるように整理することです。
部署間や担当者ごとに業務の流れが異なると、効率化は難しくなります。そこで、BPMでは業務フロー図を用いて、プロセスを統一的に示します。
これにより、作業手順のばらつきや無駄が明確になり、改善ポイントが浮き彫りになるのです。
手順2:課題を特定し改善プロセスを設計する
次に、可視化した業務プロセスを分析し、問題や非効率な箇所を特定します。改善すべき課題を具体的に挙げることで、次のアクションが明確になります。
例えば、「承認プロセスに時間がかかりすぎている」「書類のやり取りが複雑で無駄が多い」といった課題を洗い出します。
その後、改善後の新たな業務プロセスを設計します。この段階では、現場の意見も取り入れ、実際の業務に即した実践的なプロセスを構築することがポイントです。
手順3:改善プロセスの実施とモニタリングを行う
改善プロセスを設計したら、いよいよ実施段階に入ります。まずは小規模な範囲で試験的に導入し、スムーズに機能するかどうかを確認します。
改善を実施した後は、その効果を定期的にモニタリングすることが必要です。どの程度改善されたのか、期待した効果が出ているのかを数値やデータを基に評価します。
モニタリングを継続的に行うことで、問題があれば早期に対応でき、改善効果を最大化できるのです。
手順4:PDCAサイクルを継続して回す
BPMでは、改善プロセスを一度導入したら終わりではありません。継続的にPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回すことが重要です。
計画を立てて実行し、効果を測定した後に再び改善策を検討します。このサイクルを繰り返すことで、業務プロセスは常に最適な状態に近づいていきます。
PDCAサイクルを定着させることで、企業は市場の変化や新たな課題に柔軟かつ迅速に対応できるようになります。
BPMツール(BPMS)とはどのようなものか?
BPMを円滑に進めるためには、専用のツール(BPMS)の活用が効果的です。BPMSには、業務プロセスを簡単に設計・管理・改善するためのさまざまな機能が備わっています。ここではBPMSの代表的な機能について解説します。
業務プロセスを設計・可視化するモデリング機能
BPMS(ビジネスプロセスマネジメントシステム)の代表的な機能がモデリング機能です。これは業務プロセスを視覚的に設計し、誰でも理解できる形で示すためのものです。
モデリング機能を使えば、業務フロー図の作成や修正が簡単になります。専門知識がなくても操作できるため、現場の社員でもスムーズに業務プロセスを共有できるようになります。
プロセスの変更も迅速に反映できるので、柔軟な改善活動が可能になります。
業務の問題点を把握するシミュレーション機能
BPMSのシミュレーション機能では、設計した業務プロセスが実際にどの程度の効果を生むかを事前に検証できます。実際に運用を開始する前に、ボトルネックやリスクを把握できるのです。
例えば、承認プロセスにどれくらい時間がかかるか、業務負荷がどこに集中するかなどをシミュレーションで確認します。これにより、本格導入後の失敗を未然に防げます。
シミュレーションを活用することで、自信をもって新プロセスを導入できます。
業務改善の進捗を確認するモニタリング機能でPDCAを回せる
BPMSにはモニタリング機能も搭載されています。これは、改善プロセス導入後の効果をリアルタイムで監視し、評価するためのものです。
業務の進捗や処理時間、コスト削減効果などを自動的に数値化できます。PDCAサイクルを回す際に必要な情報を即座に把握できるため、次の改善活動につなげやすくなります。
この機能を利用すれば、改善活動の進捗状況を全社的に共有しやすくなり、改善意識を組織全体で高めることが可能です。
自社に適したBPMツールの選び方とは?
ツールの選び方は主に3つの観点が重要です
- 業務プロセスを可視化しやすいかどうか
- 導入後のサポート体制やコストが適切か
- 現場で利用する社員の意見を組み込まれているか
1つ目のツール選定のポイントは、業務プロセスを可視化しやすいかどうかです。現場の社員が簡単に操作でき、業務の改善ポイントを的確に把握できるツールを選ぶ必要があります。
また、導入後のサポート体制やコスト面の検討も欠かせません。継続的な改善活動には手厚いサポートが不可欠だからです。初期費用だけでなく、維持・運用コストも考慮しましょう。
最後に、実際に利用する社員の意見を反映させることも重要です。ツールの無料トライアルやデモ版を試用し、操作性や使い勝手を現場が納得したうえで選ぶようにしましょう。
まとめ|BPM導入で実現できることを再確認

ここまで、BPM(ビジネスプロセスマネジメント)について詳しく解説してきました。BPMを導入することで業務プロセスの可視化が進み、組織全体で効率的な改善活動を進めることができます。
可視化が進めば、業務の無駄やボトルネックを正確に把握できます。根本的な課題を見つけ出し、継続的な改善により生産性や競争力の向上につながります。
ただし、導入の際は目的を明確にし、現場の協力を得ることが不可欠です。ツールの選定も、自社のニーズをきちんと整理したうえで慎重に行いましょう。
BPMは、企業が激しく変化する市場環境に柔軟に対応し、競争力を維持・強化していくための重要な取り組みです。ぜひBPM導入を前向きに検討し、自社の業務改善を具体的に推進してみてください。
BPMの導入・運用には専門的な知見と継続的な取り組みが求められます。そうした取り組みを支援するパートナーとして、当社のBPOサービスもご活用いただけます。
私たちキヤノンマーケティングジャパングループは、お客さまのビジネス変革を、ITとBPOでご支援します。ご相談、お問い合わせをお待ちしております。
こちらの記事もおすすめです
関連ソリューション
「BPOソリューション」についてのご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BPO企画部